
「話す前の5秒」がくれた静かな変化
「はい、それってつまりどういうことですか?」
「結論を言いますと…」
――毎週月曜の定例会議。
誰かが話しているあいだも、僕はずっと“自分が何を言うか”ばかりを考えている。
そのせいか、出てくる言葉はどこか浅くて、
話し終えたあとには、いつも後悔と自己嫌悪が残る。
そんな自分に、あるとき小さな変化が訪れた。
それは──「話す前に5秒だけ止まる」という、たったひとつの習慣だった。
安達裕哉さんの著書
『頭のいい人が話す前に考えていること』は、
話し方のテクニックを教える本ではない。
むしろ、「話す前に、どう立ち止まるか?」
という“考えるための構え”を、静かに、しかし確かに教えてくれる本だ。
あなたは、話す前に「5秒」止まれていますか?
そのたった数秒の“間”にこそ、頭の良さと、信頼が宿る。
僕はこの本から、そんな静かな知性の正体を教わった。
気づき(黄金法則①②③)

■「反応しない」ことは、知性の始まりだった
黄金法則①「とにかく反応するな」──この言葉を読んだとき、思わずハッとした。
たぶん、僕にとっていちばん刺さったのはここかもしれない。
だって、自分の普段の反応を思い返してみたら、
ほとんどが「条件反射」みたいなものだったから。
たとえば、メールの催促にすぐ返信しなきゃって焦って打ち返したり、
会議でちょっと嫌味っぽいコメントが飛んできたら、その場でムッとした声を出してしまったり。
SNSでも、イラッとくる投稿に心がザワついて、
無言でスクショ撮って、誰かに送ったこともある。
そうやって、「反射」で返した言葉や行動って、
あとから必ず後悔してる。
「あぁ、あれは余計だったな」って。
でも、反射するのが悪いんじゃない。
大事なのは、“反射の前にワンクッション置く”**なんだと気づいた。
『反応しない練習』(草薙龍瞬)にもこう書いてあった。
「感情はあっていい。でも、それに飲まれる必要はない」
怒りも、焦りも、モヤモヤも、
湧いてくること自体は否定しなくていい。
でも、その感情に突き動かされる前に、一度立ち止まる。
ほんの数秒でいい。
深呼吸して、状況を見渡して、自分の“考え”に戻る。
その“間”があるだけで、言葉の深さが全然違ってくる。
反応する前に「考える」。
そのプロセスこそが、知性なんだと腑に落ちた瞬間だった。
■「頭の良さ」は、自分ではなく、相手が決める
昔、「ロジカルに話せば賢く見える」と思っていた。
だから会議でも、なるべく論理的に、要点をまとめて、
“できる風”の発言を心がけていた。
でも、なぜか伝わらない。
刺さらない。
手応えがない。
そんなときに出会ったのが、黄金法則②「頭の良さは他人が決める」だった。
ああ、そうか。
“自分がどう見られたいか”ばかりを気にしていたんだなと気づかされた。
相手が「あ、この人、ちゃんと考えてくれてるな」って感じるのは、
整った発言よりも、その人の“姿勢”や“向き合い方”だったりする。
たとえ言葉が少なくても、時間がかかっても、
“相手のことを真剣に考えている”という空気は伝わる。
逆に、うまいこと言ってても、それが“自分のため”に聞こえたら、一瞬で見透かされる。
知性は、自己満足じゃなくて、相手とのあいだで育つもの。
それを忘れちゃいけないんだと、この章で強く思った。
■「ちゃんと考えてくれてる人」は、信頼される
この法則③は、とても静かな言葉だったけど、
読みながら、少し胸が熱くなった。
僕がいちばん信頼している人を思い浮かべたとき、
それは「話がうまい人」でも、「仕事が早い人」でもなかった。
どんなに忙しくても、
「ちょっと考えさせてくださいね」と言ってくれて、
次に話すときには、ちゃんと僕の立場や気持ちに沿った言葉を返してくれる人。
その人の言葉はいつも、思慮深くて、あたたかかった。
たぶん、賢い人よりも、“真剣に考えてくれる人”のほうが、僕たちはずっと信頼できるんだと思う。
思いやりとは違う。おせっかいでもない。
ただ、「この人は、自分のことを本気で考えてくれたんだ」と感じること。
その実感が、信頼の正体なのかもしれない。
3つの黄金法則を読んで、僕の中にひとつの確信が生まれた。
言葉の強さよりも、沈黙の使い方のほうが、人の知性を映す。
そして、どれだけ話す内容を磨いても、「話す前に考えた時間」には敵わない。
この本が教えてくれたのは、そんな“沈黙のチカラ”だった。
3. 変化(黄金法則④⑤⑥)

■「人」と闘うな、「課題」と闘え
仕事をしていると、どうしても人とぶつかる場面がある。
たとえば、意見が食い違ったとき。
無責任な言い方をされたとき。
理不尽な指摘を受けたとき。
そんなとき、僕はつい「人」に向かってしまっていた。
あいつはわかってない、とか。
なにを偉そうに、とか。
いや、そもそもそれ、お前の責任じゃん、とか。
でも、そうやって“人を相手にしている”うちは、
本当に解くべき“問題”が、ずっと宙ぶらりんのままだった。
実際、「人と闘ってしまったな」と思う場面は何度もあった。
たとえば、前職で先輩に仕事の進め方を厳しく指摘されたとき。
「そっちだってミスしてるじゃん」と思いながら、反発するような言い方をしてしまった。
その瞬間はスッとしたけれど、あとから冷静になって思い返すと、結局は何も前に進んでいなかった。
ふと「あの案件の目的ってなんだったっけ?」と振り返ったとき、
戦うべきは“相手の態度”じゃなくて、“プロジェクトの遅延”だったと気づいた。
感情じゃなく、課題に目を向ける。
それだけで、会話の温度も、信頼関係も、少しずつ変わっていく気がしている。
そんなとき出会ったのが、黄金法則④──「人と闘うな、課題と闘え」という言葉だった。
相手を論破しても、問題は解決しない。
それどころか、信頼すら失っていく。
この考えに触れたとき、ふっと肩の力が抜けた。
そうか、僕は「勝ちたかった」だけなんだな、と。
正しさでマウントを取りたくて、
相手をやりこめて、優位に立ちたくて。
でもそれって、問題解決でも、対話でもなくて、
ただの“感情の発散”だったんだ。
それ以来、イラっとしたときはまず「この人と闘いたいのか、それとも課題を解決したいのか?」と、自分に問いかけるようにしている。
思い返せば、『嫌われる勇気』にあった“課題の分離”という概念が、ここでも生きていた。
評価は他者の課題。
自分がコントロールできるのは、自分の選択と行動だけ。
この視点を持つようになってから、
「言い返さなくてもいい」場面が増えた気がする。
それは決して“負け”ではなくて、
むしろ、“自分の土俵”にちゃんと立てるようになった、という感覚だった。
■「伝わらない」のは、話し方じゃなく“考え方が浅い”から
この言葉を見たとき、正直ちょっとグサッときた。
黄金法則⑤──「伝わらないのは話し方の問題ではない。思考が浅いからだ」
僕はずっと、“どう話せば伝わるか”を気にしていた。
プレゼンの構成、話す順番、言い回し、アイコンタクト、声のトーン…。
伝え方を磨けば、伝わると思っていた。
でも、うまく話しても、中身がスカスカなら、伝わらない。
そして、その“中身”は、話す前にどれだけ考えたかに比例する。
これは、なかなか耳の痛い真実だった。
ある会議で、僕は自分の担当案件について説明した。
それなりにうまく話せたとは思う。
でも、終了後に上司から言われたのは、「で、それって何が一番の課題なの?」だった。
……答えられなかった。
そのとき初めて気づいた。
「説明できる」と「考え抜いた」は、全然違うんだ、と。
伝える前に、もっと深く考えること。
相手に伝わる言葉は、テクニックじゃなくて、思考の深さからしか生まれない。
そのことを、自分の失敗から学んだ。
■「知識」は“与える”ことで初めて知性になる
黄金法則⑥で書かれていたのは、
「知識や情報を、自分のためだけに使っているうちは、まだ知性とは言えない」という話だった。
それを読んで、ふと自分の仕事ぶりを振り返った。
正直なところ、昔の僕はちょっと出し惜しみしていた。
調べた資料とか、いい感じのテンプレとか。
「これは自分の武器だ」と思って、あえて共有せずに取っておいたりして。
でも、それって結局、
“信用を削って、自分だけが得を取ろうとしてる”行為だったんだよな、と今では思う。
そんな自分を変えたのが、アダム・グラントの『Give & Take』だった。
与える人(Giver)は、短期的には損して見えるけど、
長期的には、最も大きな信頼と成果を得る。
この理論を知ってから、週報や調査メモ、使いやすかったスライドテンプレなんかを
積極的に社内でシェアするようになった。
すると、不思議なことに、
人が自然と集まってくるようになった。
「これってどうやってやったの?」とか、「この前のやつ参考になったよ」とか。
頼られることが増えた。声をかけられることも、相談されることも増えた。
そして何より、
「自分は、誰かのためにちゃんと働けてる」って感覚が、生まれた。
知識は、“抱える”ものじゃなくて、“流す”ことで活きる。
それが、ようやく腑に落ちてきた。
この3つの法則を読んで、
僕の中でじわじわと何かが変わり始めた。
「闘う相手を間違えないこと」
「思考を浅く終わらせないこと」
「自分だけのために溜め込まないこと」
それぞれは小さな意識の変化かもしれないけれど、
この積み重ねが、「信頼される人」や「思慮深い人」への道なんじゃないかと、今は思う。
■ 承認されたいなら、まず“与える側”にまわる

会議で発言するとき。
SNSで何かを投稿するとき。
上司に提案を出すとき。
──どこかで、誰かに認められたいと思っている。
「すごいね」「助かったよ」「よく気づいたね」
そんな言葉が、心のどこかで待っている自分がいる。
でも、安達さんが本の中で伝えていた黄金法則⑦は、
そんな自分の承認欲求を否定するものではなかった。
「承認欲求は満たすものではなく、与える側にまわること」
これは、僕にとってすごくやさしくて、力強い言葉だった。
誰かに認められたいと思うのは、自然なこと。
でも、いつまでも「承認されるのを待つ側」でいると、
心が削れていく。評価に振り回される。結果が出ないと自信が消える。
じゃあ、視点を変えてみよう。
「認めてほしい」から、「誰かを認める」側に。
自分の中に湧いた“いいな”を、ちゃんと口に出す。
誰かの努力や工夫に、ちいさな「ありがとう」を返す。
思いついたアイデアを、まずは誰かにプレゼントしてみる。
すると、承認されること以上に、心がじんわりあたたまる瞬間が生まれる。
それは、自分の中に残る“小さな誇り”のような感覚だった。
▶ 明日からできる3アクション
理屈だけじゃなく、日常に落とし込んでみる。
そうすることで、この本の学びは“自分の一部”になっていく。
ここでは、僕自身が実践して変化を感じた3つのアクションを紹介したい。
1. 5秒ルールの導入:思考の“間”をつくる
これはもう、超シンプル。
スマホの壁紙に
「深呼吸 → 考える → 話す」と表示しておく。
あるいはPCのポストイットでもOK。
人と話す前、反射的に返したくなる前、
ほんの5秒、間をつくるだけで、言葉の質が変わる。
言い過ぎなくなるし、噛み合わない会話も減るし、
なにより、自分の言葉に“責任”を持てるようになる。
ある月曜の定例会議、いつものように「何を言おうか」を考えていたけど、
その日は5秒、黙って“みんなの話”に耳を傾けた。
すると、思ったよりも話がかぶっていたり、すでに誰かが同じ懸念を出していたりして、
自分が出すべきは“まとめ”や“提案”だと、自然と見えてきた。
あのときの5秒が、僕に「今の会話の流れ」を考える余裕をくれた。
2. 課題の分離ノート:感情のバウンスを止める
上司の一言にイラッとしたとき、
「それって本当に“自分の課題”だろうか?」と問い返す習慣。
ノートに線を引いて、
自分の課題
相手の課題
を分けて書くだけでも、頭が整理される。
書き出してみると、案外「それ、私が背負わなくてよかったんだな」って思えることが多い。
感情は、整理されると静かになる。
バウンスしなくなる。
自分の“平和”を守るためにも、これはすごくおすすめ。
3. 週1ギブ・チャレンジ:まず渡す、を習慣に
週に1回、「これは誰かの役に立つかも」と思った情報や資料を、
“誰かのために”シェアしてみる。
・役立った記事をチームチャットに投稿
・つくったExcel関数を使い回せるようにフォルダ共有
・新人さんへのTipsメモを作っておく
最初は反応がなくてもOK。
「まず渡す」を続けていくと、信頼がちょっとずつ積み上がっていく。
与えたものは、巡ってくる。
ただし、それは“ギブした瞬間”ではなく、“あなたの言葉が信用され始めた頃”に。
3つのアクションは、どれもすぐに始められる。
でも、どれもじわじわと効いてくる。
変わるのは、言葉じゃない。言葉を発する自分自身だ。
話す前に考えていること

この本が教えてくれるのは、
「話す技術」ではなく、“話す前の姿勢”と“考え方の深め方”。
それは、相手に伝えるための技術ではなく、
信頼を育てるための在り方と言い換えてもいいかもしれません。
ここでは、本書の核心である7つの黄金法則と5つの思考法を、簡潔に振り返ります。
🔸「7つの黄金法則」── 知性と信頼を生む“話す前の心得”
| No. | 黄金法則 | 解説 |
|---|---|---|
| ① | とにかく反応するな | 感情で即答せず、5秒の“間”を置くことで思考が深まる |
| ② | 頭の良さは他人が決める | 自分視点ではなく、相手に“どう映るか”がすべて |
| ③ | 人は「ちゃんと考えてくれている人」を信頼する | 賢さより“真剣さ”が信頼の根になる |
| ④ | 人と闘うな、課題と闘え | 相手ではなく“問題”を一緒に解決する姿勢が大切 |
| ⑤ | 伝わらないのは、話し方ではなく考え方が浅いせい | 話す前に「どれだけ考えたか」が言葉の説得力を左右する |
| ⑥ | 知識は誰かのために使って初めて知性 | 自分だけで使う知識は“賢さ”に留まり、他者に使うことで“知性”になる |
| ⑦ | 承認欲求は満たす側に回れ | 認めてもらいたいと願うより、先に誰かを認めることで関係が変わる |
🔸「5つの思考法」── 話す前の“脳の筋トレ”
| No. | 思考法 | 解説 |
|---|---|---|
| ① | 客観視 | 感情を脇に置き、事実と主観を切り分ける力 |
| ② | 整理 | 結論・根拠・具体例を整理して“思考のかたまり”を整える |
| ③ | 傾聴 | 相手の立場に立ち、背景や思考の流れを理解しようとする姿勢 |
| ④ | 質問 | 相手を動かすのは主張ではなく、問いかけの力 |
| ⑤ | 言語化 | 抽象⇄具体を行き来しながら、自分の思考を“言葉”に変えるスキル |
この2つのフレームを、会話や仕事の前にほんの少し意識するだけで、
言葉の質が変わり、周囲の反応が変わり、自分自身のあり方まで変わっていく──
本書を読んで得た一番の収穫は、そこにあると思います。
まとめ
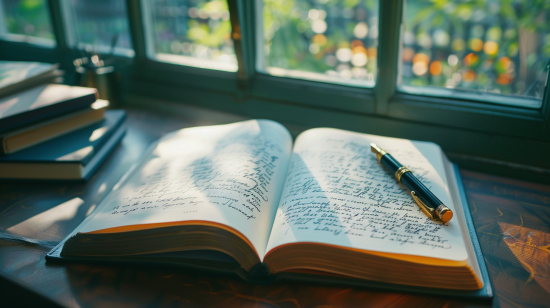
「賢い話し方」や「ロジカルシンキング」って、
たしかに、便利だし、評価もされやすい。
でも──それだけじゃ、届かないことがある。
本当に大切なのは、
“話す前に何を考えていたか”
そして、その言葉に、どんな思いを込めたのか。
誰かを動かすのは、正解ではなく、真剣さだ。
伝わるのは、技巧ではなく、思考の深さと体温だ。
あなたは次に口を開く前、
ほんの数秒でいいから、立ち止まってみてほしい。
何を考えますか?
誰のために、その言葉を届けますか?
その“間”にこそ、
あなた自身の知性と優しさが、きっと滲み出る。
編集後記
この記事では、安達裕哉さんの『頭のいい人が話す前に考えていること』を、
心理学や名著の視点と絡めながら、僕なりの体験と言葉で紐解いてみました。
反応を遅らせること。
評価に振り回されないこと。
言葉の前に、考えを育てること。
この本が教えてくれたのは、
「話すこと」の奥にある“静かな思考の力”でした。
ぜひあなたも、この本を手に取り、
次に誰かと話すその前に、
“たった5秒の沈黙”を、自分に贈ってみてください。
きっと、世界が少しだけ、優しく変わって見えるはずです。


