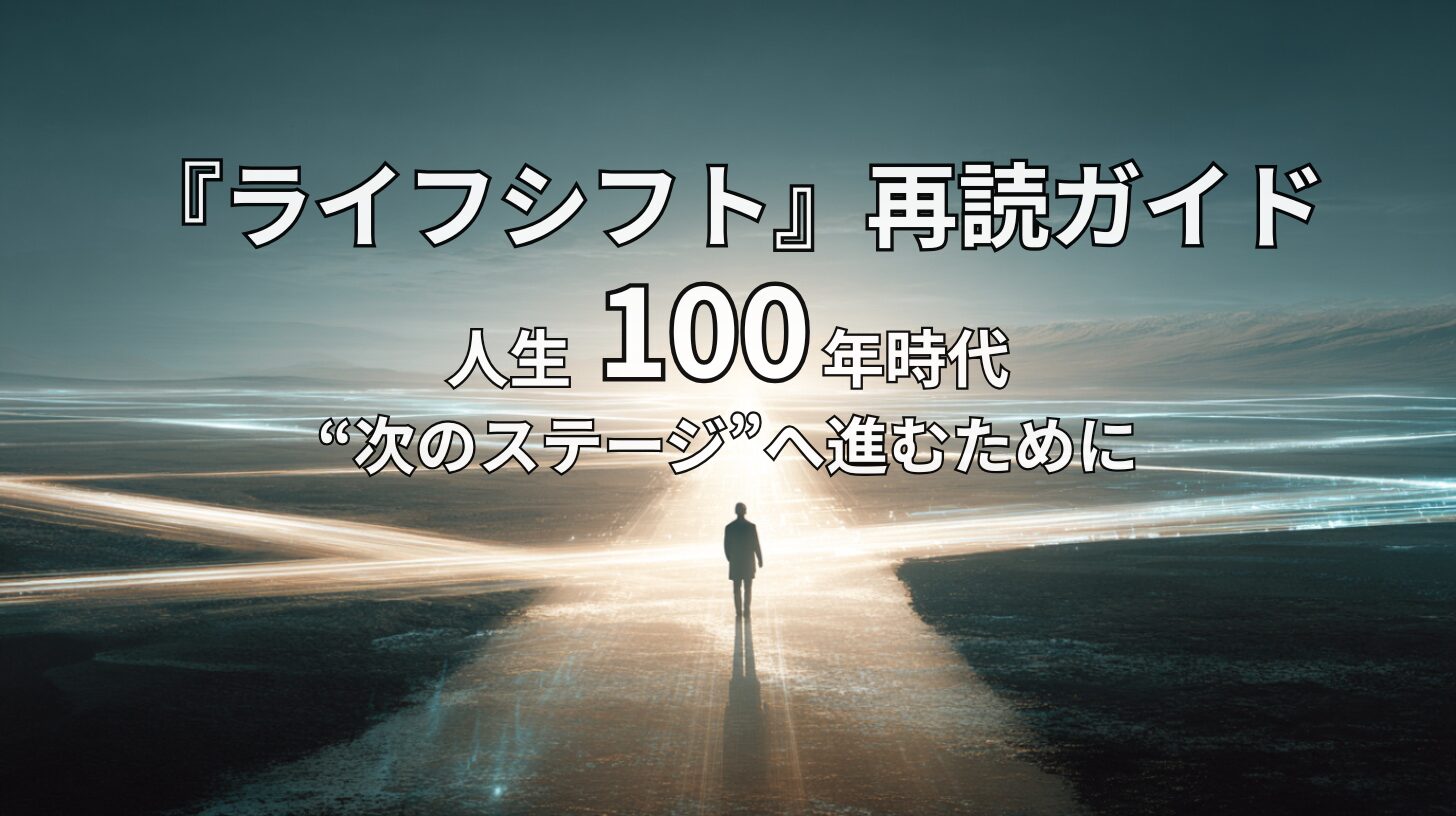目次
今こそ「未来戦略」が必要な3つの理由

──あなたの“人生設計図”、最後に更新したのはいつですか?
昭和の頃から続く“65歳定年モデル”は、静かにその役目を終えつつあります。
そして、気づけば“人生100年時代”は未来ではなく、私たちのすぐ目の前にあります。
ここで問われるのは、
「どうやって生き延びるか」ではなく、
「どう再設計するか」という発想です。
いま、なぜこのテーマに再び注目すべきなのか?
その理由は、以下の3つの変化に凝縮されています。
1|長寿インフレが始まっている
2025年、日本の平均寿命は男性81.09歳・女性87.14歳。
次の節目は「90歳時代」。しかも、健康なまま迎える人が激増している。
これまでの“老後20年”モデルは、もはや現実からズレている。
80歳で働き、90歳で学び直すような人生が、普通の選択肢になっていく。
2|AI × ヘルスケアの進化が「生き方」を変える
バイオテック、ウェアラブル、AI診断、デジタルセラピー……
技術の進歩は「命を救う」から「人生を最適化する」フェーズへ。
健康寿命を延ばす技術とデータ活用が、
「いつまで働けるか」ではなく「どんな人生を創るか」を左右する時代に入った。
3|制度サイドが、ようやく動き始めた
- 70歳までの就業指針
- 金融教育の義務化
- 学び直し支援(リカレント教育)の加速
- 企業の「健康経営」認証拡大
これまで“個人の問題”だった人生設計が、国家レベルのアップデート対象に。
組織も個人も、先回りして「再設計力」を磨く必要が出てきている。
『LIFE SHIFT』から何が“進化”したのか?

2016年、世界に衝撃を与えた『LIFE SHIFT』。
あれから約10年。進化したのは「人生」だけではありません。
社会全体の設計図が、いま大きくアップデートされようとしています。
その最新版が、アンドリュー・スコットによる本書
『ライフシフトの未来戦略(原題:The Longevity Imperative)』です。
では、前作と比べて何が新しくなったのか?
✔ ① コンセプトの進化|Evergreen Economy
本書で新たに提示されたキーワードが「Evergreen(常緑)」。
これは、「人も社会も再生可能な存在として設計し直そう」という提案です。
人生100年時代を、健康・学び・働き・つながり・意味の5つのレンズで再定義。
“延命”ではなく、“再設計”の視点が貫かれています。
✔ ② 構成の進化|3部構成で戦略的に整理
第Ⅰ部|「新しい必須課題」── 長寿化に向き合う基盤の再設計
第Ⅱ部|「エバーグリーン経済」── 経済・金融・雇用のOSアップデート
第Ⅲ部|「エバーグリーン社会」── 地域・つながり・意味の再構築
『LIFE SHIFT』が描いたのは“個人の選択肢”。
『The Longevity Imperative』はそこから一歩踏み込み、
社会全体の再設計と制度実装にフォーカスしています。
✔ ③ アクションの進化|“5レンズ”で具体化
| レンズ | 意味 |
|---|---|
| Healthspan(健康寿命) | 医療→予防へ。長く活動できる体の設計。 |
| Skills(スキル) | リスキリング&学び直しで「何歳でも現役」に。 |
| Finance(金融) | 寿命90年に対応する“長生き設計”への転換。 |
| Community(つながり) | 孤立を防ぐ「共生の設計」。 |
| Meaning(意味) | なぜ働くのか。なぜ学ぶのか。“生きる理由”の再定義。 |
個人のライフシフトだけでなく、社会のルールブックそのものを更新する。
それがこの本の最大の進化です。
『未来戦略』を支える5つのピラー

長寿社会の再設計に必要なのは、「問題解決」ではなく新しい設計図です。
本書では、人生100年時代に対応するための5つの戦略ピラー(柱)が提示されます。
それぞれ、海外の概念と日本の実情を照らし合わせながら見ると、
社会の“次の一手”がクリアに見えてきます。
| 🧱 ピラー | 🔑 キーワード | 日本的論点 |
|---|---|---|
| ❶ 健康革命 | Preventive Tech / ヘルススパン | 健診のデジタル化、メタボからフレイル予防へ。「病気にならない社会設計」へと転換中。 |
| ❷ 経済的配当 | Longevity Dividend | 長生きを前提に、年金・NISA・保険制度を再編。「長寿インフレ時代の資産運用」が焦点に。 |
| ❸ 働き方再設計 | Evergreen HR | 70歳雇用が現実に。「年齢に応じた選べる働き方」が企業制度に求められる。 |
| ❹ 人生の意味 | Purpose Capital | 退職後の孤立を防ぐ地域共創型のコミュニティ設計へ。“セカンドライフの主語”を「自分」に戻す時代。 |
| ❺ 世代間課題 | Inter-generational | 相続税や教育制度の見直し、多世代で暮らす設計が住宅・都市政策に組み込まれ始めている。 |
これらのピラーは単なる政策の話ではなく、
企業のビジネスチャンスであり、
個人のライフデザインの問いでもあります。
❶ 健康革命|Preventive Tech/ヘルススパンの延伸
「長く生きる」ではなく、「長く健康に生きる」社会設計へ。
▍何が変わるのか?
従来の「病気を治す」医療から、「病気にならない」予防医療へとパラダイム転換。
食・運動・睡眠・メンタルヘルスをテクノロジーで可視化・管理。
AIによる健診DX(予測・早期発見)や、スマートウォッチ×保険の連動が進む。
▍日本では?
「メタボ健診」から「フレイル予防」へ:高齢期の虚弱を未然に防ぐ取り組みが各自治体でスタート。
経産省の「健康経営銘柄」、ヘルスケア産業化の波が本格化。
ケア領域では、介護予防×DXやロボット導入が進行中。
▍個人の問い
健康は“努力”ではなく“戦略”になっている。
テックを活用し、「日常に仕組みとして健康を埋め込む」生き方へ。
❷ 経済的配当|Longevity Dividend(長寿からの利益)
「老後資金」ではなく、「長寿から得られる資産設計」へ。
▍何が変わるのか?
長寿=支出が増える という恐怖から、長く働き・学び・分かち合える価値創造の時代へ。
働く時間の延長で、リスク資産への運用・副業・共助モデルが重要に。
▍日本では?
積立NISA、iDeCo、長寿保険(終身収入型)の市場が急拡大。
金融リテラシー教育が高校で必修化。人生全体での資金計画が常識に。
リバースモーゲージ・地域通貨など、多様な資産活用策が登場。
▍個人の問い
「90歳まで生きる前提で、あなたの資産設計は適応していますか?」
❸ 働き方再設計|Evergreen HR
「引退する前に、役割を変える」柔軟なキャリアの再設計へ。
▍何が変わるのか?
定年・年功序列・一括採用の“昭和型モデル”から脱却。
人生の後半でも、「価値を発揮できる働き方」を選べる社会へ。
キャリアは“階段”ではなく、“連続する曲線”に。
▍日本では?
70歳就業指針、選択定年制の導入が進む。
副業解禁・ジョブ型雇用・週3勤務など、柔軟化が現実に。
「越境学習」や「プロボノ副業」で、組織外の価値提供が評価される。
▍個人の問い
今の働き方は、80歳まで続けられますか?
体力・知識・好奇心を“持続可能化”できる環境設計を。
❹ 人生の意味|Purpose Capital
「何のために生きるか」が、最も重要な資産になる時代。
▍何が変わるのか?
キャリアの中心が「安定」から「貢献」へ。
退職後こそ“第2の挑戦”が始まる、という前提へ。
「所属」よりも「参加」「つながり」「物語」が意味を生む。
▍日本では?
NPO/地域活動/パラレルキャリアが中高年層に広がりつつある。
定年後の孤立対策として、「学び直し×地域共創」の動きが行政でも進行。
AI時代の“意味資本”として「人の役に立てる感覚」が再評価。
▍個人の問い
あなたは“引退後”、何を成し遂げたいですか?
「意味のある余白」を、自分で設計できる時代です。
❺ 世代間課題|Inter-generational
「高齢者の時代」ではなく、「全世代で支え合う設計」へ。
▍何が変わるのか?
相続・介護・教育・住宅設計すべてが、世代を超えて再設計され始めている。
「分断」ではなく「混ざる」ことで生まれる、相互理解と共創。
▍日本では?
コリビング、地域型大学、シニア×学生の混成拠点などが各地で誕生。
相続税や扶養制度なども見直しが議論中。
高齢化は孤立ではなく、新しい共創の起点になりうる。
▍個人の問い
子世代・親世代・地域との「接点」をどれだけ持てていますか?
“再設計する社会”の最前線は日本にある

「長寿」はリスクじゃない。
正しく備えれば、“やり直す”ための時間資産になる。
❶ 超・長寿社会のリアルと転機
世界で最も早く高齢化に直面した国、それが日本です。
2023年の平均寿命は、男性81.09歳、女性87.14歳。
国連の推計では、総人口の約10%が80歳以上となる社会がすぐそこまで来ています。
労働人口の減少、年金制度の限界、介護人材の不足——
ネガティブな話題が先行しがちなこの現状に、Andrew Scottはこう問いかけます:
“長く生きる”ことを、悲観ではなく再設計の好機として捉えられるか?
この視点に立ったとき、見えてくるのは日本の“希望の兆し”です。
❷ “希望の兆し”が実装され始めている
| 領域 | 変化の兆し |
|---|---|
| 高齢者の就労 | 就労率25%超(OECD最高水準)。定年延長・再雇用・越境副業など、就業モデルが多様化。 |
| 健康・ウェルビーイング | 経産省「健康経営」指標の普及。ヘルススパン(健康寿命)重視の医療×テックが進行。 |
| シニア消費 | 年間100兆円市場。“成熟世代向け”という新たなカテゴリで、旅行・投資・学び需要が急増。 |
| ケアの進化 | 介護ロボ/AI見守り/在宅支援VRなど、Age-Techの現場実装がスタート。 |
❸ “成長因子”としての長寿:3つのビジネスレイヤー
① Age-Tech(エイジテック)市場
転倒センサー、スマート補聴器、服薬IoT、認知症VRトレーニング…
“高齢を前提としたテック”=次のユニコーン市場
日本の現場ニーズが、世界標準のUI/UX設計を先導できる
② Evergreen UX:あらゆるUI/UXの再設計
金融・自治体・Eコマース・医療に至るまで、「老い」を前提に設計されたUXはまだない
見えづらさ、操作しづらさ、迷いやすさをなくす設計が、全世代に恩恵をもたらす
③ 多世代共創コミュニティ
高齢者だけを囲うのではなく、“世代を横断する場”をどう設計するか
地方移住+介護シェアハウス/オンライン大学/地域型プロボノなど
「学び・働き・ケア」が共存する共創空間は、社会の分断を癒す新モデルへ
“制度疲労”を超えて、「社会のOS」を更新する
日本は、世界がまだ見ぬ「長寿社会のOS」をアップデートできる唯一の国かもしれない。
人口構成が変わるのは避けられない。
でも、その変化を「衰退の兆し」と見るか、「再設計の始まり」と見るかで、未来はまるで違うものになる。
『The Longevity Imperative』は、まさにその分岐点に立つ私たちに、問いかけます:
“あなたの人生は、何度でも書き換えられる”
社会もまた、同じではないか?
“長い人生”は、「もう一度、始める」ための時間

『ライフ・シフトの未来戦略』は、
長寿を“延命”から“再設計”に変える、未来の取扱説明書。
私たちは、かつてない長さの時間を与えられた。
それは、ただ老いるためではない。
何度でも「やり直す」ための時間だ。
キャリアを再構築する。
人間関係を育み直す。
学びや好奇心にもう一度火を灯す。
長く生きることは、自分という物語を何章にも分けて描けるということ。
そして今、その舞台装置としての社会もまた、書き換えを迫られている。
就労制度、医療、金融、地域…
未来のOSを、誰かが先に設計しなければならない。
それが、世界で最初に高齢社会に突入した日本の役割であり、可能性なのだ。
“未来は、再設計できる。”
本書は、そのための「青写真」であり、
今日から踏み出せる「実装マニュアル」でもある。