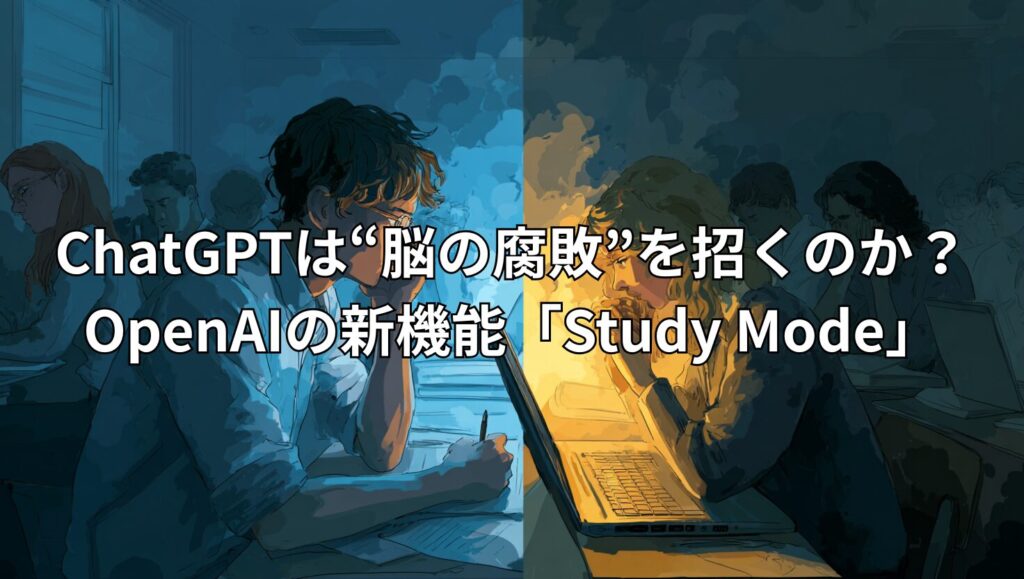
目次
ChatGPTは「ズル」なのか?
「ChatGPTでレポート書いたら単位落ちたらしいよ」
「卒論も生成AIでやったって堂々と言ってた」
そんな話題も耳にするようになった。
正直なところ、僕自身はその是非について簡単に結論を出せないでいる。
AIを使うことが“ズル”になるかどうかは、その使い方次第だと思うからだ。
そもそもChatGPTって、
ただ便利なだけのツールじゃない。
それなりの知識や、問いを立てる力、言語センスがなければ、うまく活かせない。
だからこそ、うまく使えば「巨人の肩に乗る」ような、ものすごく心強い存在にもなる。
とはいえ、勉強のしかたは確実に変わりつつある。
何を学ぶか、どう学ぶか、どこまで自分で考えるのか──
これまで“当たり前”だったことが、当たり前ではなくなっていく予感がある。
そんな中で出会ったのが、OpenAIのポッドキャスト。
エピソード4「教育とAI」を聴いたとき、僕は不意に、手が止まった。
「ChatGPTは“答えを出すAI”ではなく、“考えさせるAI”になりつつある」
「そのために開発されたのが“Study Mode”という新機能です」
──これは、使わないといけない。
そう思わされたのは、単なる機能の話ではなく、学び方そのものが問われているような気がしたからだ。
この記事では、実際にStudy Modeを使ってみてわかったこと、
「これは“答えを得る”のではなく、“考える習慣”をつくるAIだ」と感じた理由を、言葉にしてみたい。
「答え」を与えるAIではなく、「考えさせる」AIへ
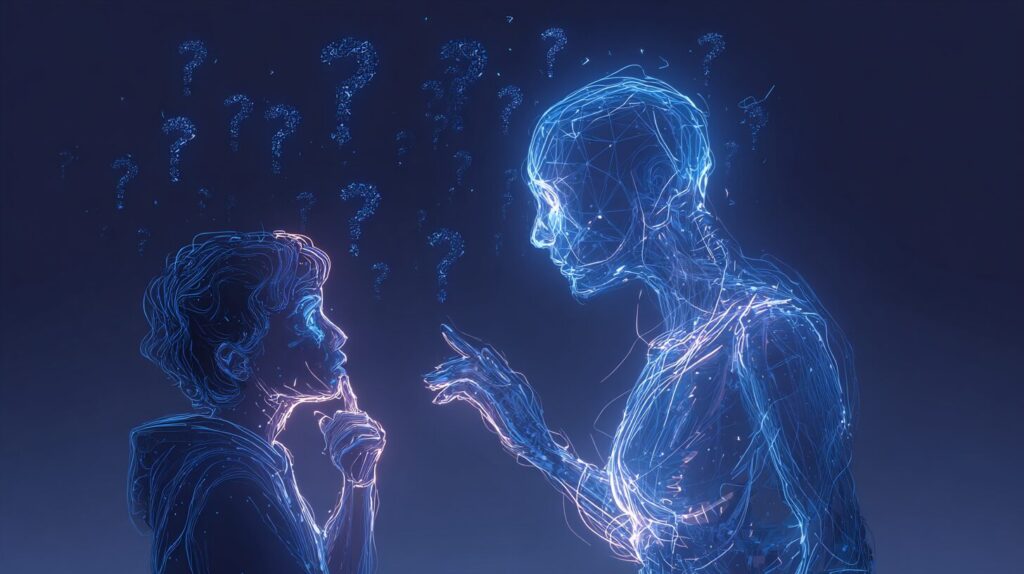
OpenAIポッドキャストで、教育責任者のLeah Belsky氏はこう語っていた。
「Study Modeは『答えを教える』のではなく、問い返して考えさせるモードです」
この言葉にハッとした。
ChatGPTといえば、質問すれば即座に答えをくれる──
そんなイメージを持っていた自分にとって、この機能はまったく新しい体験だった。
実際にStudy Modeを使ってみると、
「AIで学ぶ」というより、「AIに学ばされる」ような感覚になる。
こちらが質問しても、即答は返ってこない。
代わりに返ってくるのは、こういった問いかけだ。
「どんな目的で学びたいですか?」
「このテーマについて、どの程度理解していますか?」
「どこでつまずいていますか?」
まるでソクラテスのように、答えを与えるのではなく、“問いで思考を引き出す”。
あるいは、何時間付き合っても疲れない、無限の体力を持った家庭教師のようでもある。
「脳を甘やかさないAI」──
それが、Study Modeという“もうひとつのChatGPT”の正体だった。
実際に使って思った「問い返し」と「記憶チェック」

試しに、「生成AIについて学びたい」とStudy Modeに話しかけてみた。
すると返ってきたのは、こんな質問の数々。
どの分野に興味がありますか?(例:LLM、画像生成、倫理など)
どの程度知っていますか?
学んだあと、それをどう活用したいですか?
最初は「え、答えてくれないの?」と思った。
でもすぐに気づく。
「そもそも自分、何を知りたいのか、ちゃんと分かってなかったな」と。
その瞬間、ちょっとだけ脳が動いた感覚があった。
そして驚いたのは、数分後。
話題が進んだ頃に、Study Modeがこう言ってきた。
「ところで、さっきの“教師あり学習”って覚えていますか?」
──完全に不意打ちだった。
まるでこちらの“忘れかけタイミング”を見計らったような小テスト。
記憶の定着に大切な「再認テスト」を、自然に差し込んでくる。
これはもう、“ただの会話型AI”ではない。
「記憶に残すためのAI」として、確かな設計思想を感じた。
なにより、このやりとりがゲーム感覚で、ちょっと楽しい。
Study Mode、まずはこれで始めてみて
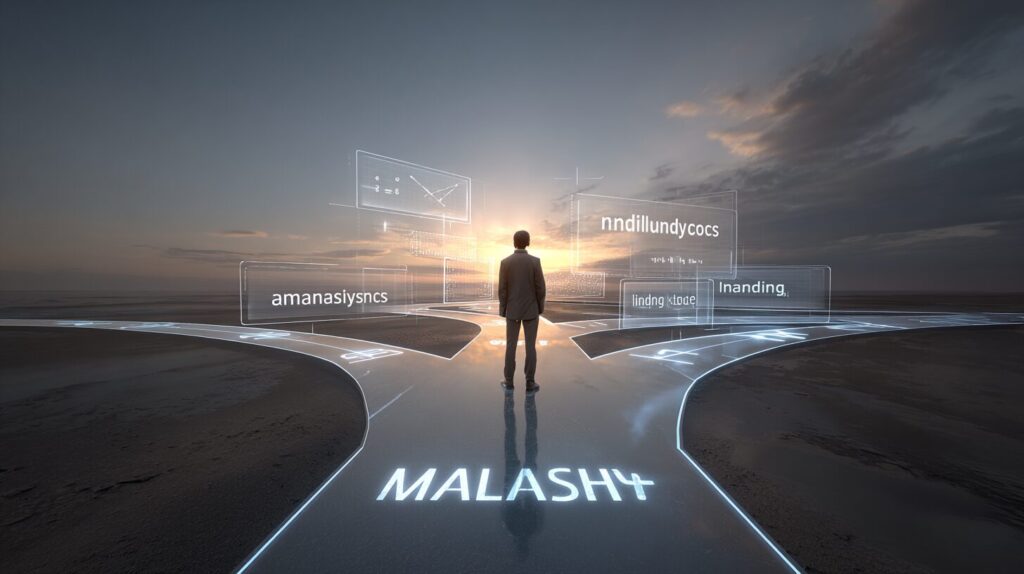
「ちょっと面白そうかも」と思ったら、試してみるのがいちばん早い。
Study Modeは無料で使えるし、特別な準備もいらない。
Study Modeのはじめ方(無料OK)
ChatGPT(GPT-4)にアクセスする
モード選択から「Study Mode」を選ぶ
「〇〇を学びたい」と入力(ざっくりでOK)
あとは返ってくる問いかけに答えていくだけで、自然と“深く学ぶ”体験が始まる
ここで大事なのは、「とりあえず聞く → 教えてもらう」ではなく、「自分の理解に合わせて導かれる」という学習プロセスがあること。
ただの受け身ではなく、自分の考えを言語化することを求められるから、思考のトレーニングとしても優れている。
おすすめテーマ例
苦手な数学・化学の単元
→「どこでつまずいたのか」を引き出してくれるので、苦手意識の正体がわかるファシリテーションや論理的思考などのビジネススキル
→ケースベースで「どう考えるか」を一緒に考えてくれる。転職・キャリアにも◎日本語の文法や読解
→母語でも曖昧になりがちなルールや構造を、対話的に見直せる就活の自己分析や志望動機の掘り下げ
→「なぜそう思ったか?」「他の可能性は?」と問いかけられることで、自己理解が深まる
どれも共通するのは、“正解を一つ求める勉強”ではなく、“自分なりの答えを探す学び”に向いているということ。
つまり、Study Modeは、「覚える学び」ではなく「考える学び」にシフトしたい人にぴったりの道具だ。
AIで学ぶ時代に、私たちが問うべきこと

いま、AIは「答えを出す存在」から「考えさせる存在」へと進化しつつある。
それは、単に便利なツールが登場したという話ではない。
学びの“前提”そのものが変わろうとしている。
「AIを使うかどうか」ではなく、
「どう使えば、もっと深く考えられるか」
──それを試されているのは、AIではなく、私たち自身なのかもしれない。
Study Modeは、そんな問いに静かに応えてくれる存在だった。
どこまでも付き合ってくれる相手と一緒に、自分の思考を深めていく。
そんな“学びの形”が、これからもっと当たり前になっていく気がする。
AIは“脳の腐敗”をもたらすのか?
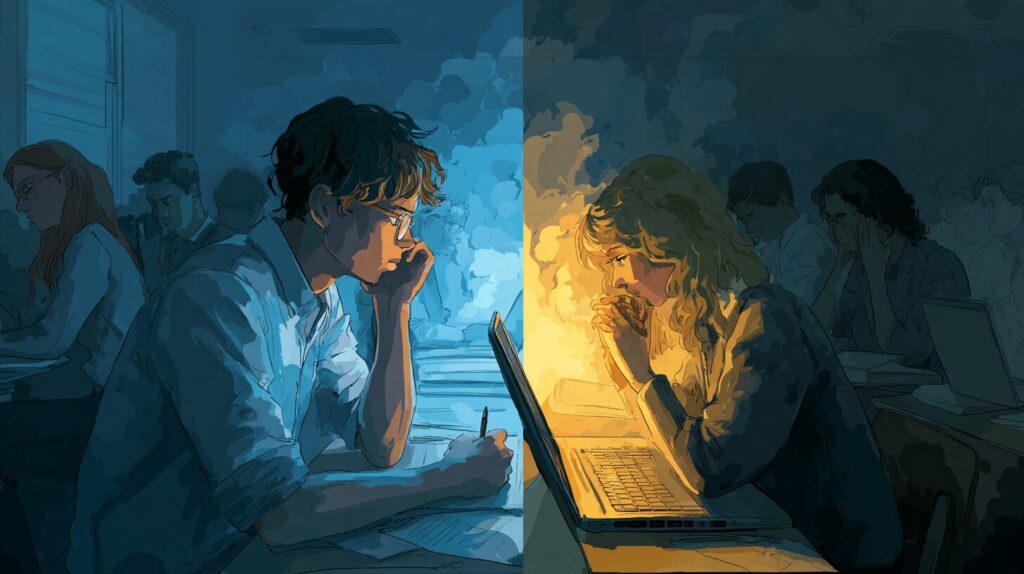
「ChatGPTを使ったら、もう考えなくなるんじゃないか?」
「学生の思考力が落ちるのでは?」
──そんな懸念を耳にすることが増えてきた。
たしかに、AIに丸投げして答えだけをコピペするような使い方では、何も残らない。
それはまるで、マラソンの練習中にスクーターで走っても、脚力はつかないのと同じだ。
でも、問題は“AIを使うかどうか”ではなく、“どう使うか”にある。
Study Modeのように、あえて即答を避け、「なぜ?」「どう思う?」と問い返してくるAIは、
むしろ思考力や記憶力、自己理解を深めてくれる“学びの伴走者”になってくれる。
「自分は何を知らないのか」
「なぜ、それを学びたいと思ったのか」
そんな問いに向き合わされる時間こそ、学びの本質なのかもしれない。
AIは、「答えを出す存在」から「考えさせる存在」へと進化している。
学びの前提が変わりつつある今、それを試されているのはAIではなく、私たち自身だ。
思考を奪われるか。
それとも、AIと共に“考える力”を鍛えるか。
分かれ道は、使い方ひとつで決まってくる。
【参考動画】

