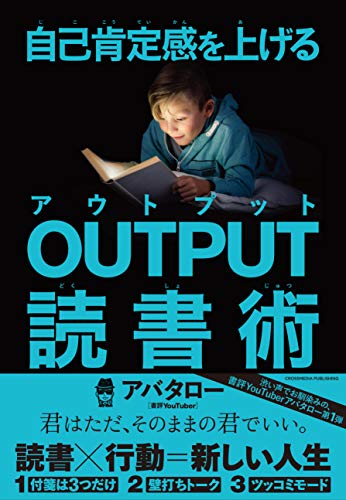
「読んでも忘れる」「いい本だったけど、何も変わらなかった」──そんな読書の悩み、ありませんか?
僕もかつて、読書が好きなのに、全然自分の糧になっていない感覚がありました。
でもある一冊と出会って、読書の仕方がガラッと変わったんです。
それが、YouTubeで書評を発信しているアバタローさんの著書
『自己肯定感を上げるOUTPUT読書術』。
この本は、「本を読んだあと、どう行動に移すか」という“読書後”の時間にフォーカスした実践書です。
読書初心者から中級者、そして「読書をもっと意味のある時間にしたい」と思っているすべての人におすすめの一冊。
本記事では、僕自身の体験も交えながら、
✅ なぜOUTPUT型読書が人生を変えるのか
✅ 誰でも真似できる具体的な4ステップ
✅ さらに深めるための“ツッコミ読書術”と“付箋マネジメント”
について、わかりやすく要約・解説していきます。
「本を読んで終わりにしない」読書法が、あなたの中で一つの“習慣”として残るように──
それでは、いきましょう!
目次
OUTPUT読書術の全体像:「読んで終わり」にしないための4ステップ

「自分のペースを崩さないこと」ー これがOUTPUT読書術の大原則です。
出典:自己肯定感を上げる OUTPUT読書術
読書は「知識の摂取」ではなく「自分の人生にどう活かすか」がすべて。
アバタローさんはそのための基本フローを、こうまとめています:
OUTPUT読書術の4ステップ
準備:集中できる環境を整える
読解:全体像から読む。最初に“オチ”をつかむ
要約:線を引いた箇所や気づきを自分の言葉で整理
発信:メモ、SNS、ブログ、誰かに話す…なんでもOK!
体験からの気づき
僕自身、この4ステップを意識するようになってから、読書の満足度が激変しました。
たとえば以前は、1冊読んでも「ふ〜ん」で終わってしまうことが多かったんです。
でもこの方法を試してからは、
最初に「どんな結論があるんだろう?」と予想しながら読む
気づきをまとめて3行で書く
誰かに「これ面白かったよ」と話す(or ブログに書く)
──それだけで記憶にも残るし、自分の言葉にすることで「理解できた実感」が得られました。
読書で変えたいのは「情報量」ではなく「行動」
アバタローさんが何度も強調するのは、
「読書量や知識の多さじゃなく、いかに自分の行動を変えたか」 ということ。
だからこそ、読書の成果を「フォロワー数」や「読了冊数」で比べるのではなく、
「昨日の自分と比べる」というスタンスが大事なんです。
実際、本を読んだあとに自分に問いかけてみてください。
「で、何をやってみた?」
「これからどう変えてみようと思った?」
その答えこそが、読書の“本当のアウトプット”になるのだと思います。
発信が記憶に定着させる近道。恥ずかしがらずにチャレンジ!
アバタロー式「ツッコミ読書術」:思考を深める3つの問い

読書で大事なのは「受け取る」だけでなく、「問い返す」こと。
アバタローさんはそれを「ツッコミモード」と呼び、読書を対話的にする3つの視点を紹介しています。
1|問い:そもそも、なぜこの本を書いたの?
これは何のための本?
誰に届けたいの?
著者の問題意識はどこ?
…と、まるで著者にインタビューするような気持ちで本に接すると、
“言いたいことの核心”がグッと見えてきます。
体験談
読書初心者のころ、僕は「著者の主張」を読み流していました。
でもこの問いを立てるようになってから、
「この人、過去にすごく挫折してたんだな」
「たった一行に全部が詰まってるじゃん」と、
背景ごと読み取れるようになったんです。
2|主張:「本当にそう?」と一度立ち止まる
本を読むとき、人はつい「書いてある=正しい」と思いがち。
でもアバタローさんは、
「主張には必ず“仮説”としての側面がある」と言います。
「なぜそう言えるの?」
「自分にはどう当てはまる?」
「反対の立場だとどう感じる?」
こうしたツッコミを加えることで、読書は受け身から能動へと変わります。
3|根拠:「なぜなら〜」の部分に注目する
著者の主張には、必ず“根拠”があります。
統計や研究結果?
自身の経験?
他者の引用?
それらを見分けながら、「自分が納得できる根拠か?」をチェックしましょう。
書あるある
「根拠が弱いな」「この体験、特殊すぎない?」
と思ってもOKです。
すべてを鵜呑みにせず、一度“自分フィルター”を通して読むことで、
読書はより“血肉化”します。
ツッコミ=違和感の棚卸し
この「問い/主張/根拠」にツッコミを入れる習慣ができると、
本を読んだ後に、
「自分はどこに納得し、どこに違和感を覚えたのか」が明確になります。
結果として、発信(ブログ・SNS)での一言目が浮かびやすくなります。
✔️「この本は○○って書いてたけど、自分は△△と感じた」
✔️「著者の主張は納得。でもそれを全員に当てはめるのは違う気がした」
──そんな感想を持てるようになれば、もう“自分だけの読書”になっています。
アバタロー式「付箋3枚ルール」:取捨選択が読書を深める

どこに線を引くか、どこに付箋を貼るか。
読書は「選ぶ力」が問われる行為でもあります。
アバタローさんが提唱するのは、
“ペンは著者の大事なこと、付箋は自分にとって大事なこと” という考え方。
そして、その付箋を「たった3枚」に絞るというルールです。
📌 そもそも、なぜ「付箋を貼る」のか?
読書中にたくさん線を引いても、
「どこが一番大事だったか?」は意外と曖昧なまま。
だからこそ、章ごとにいったん振り返り、
「自分にとって刺さったページ」に1枚ずつ付箋を貼る。
これを全章で行ったあとに──
✅ 最終的に3枚だけ選び抜く
というルールを設けます。
💡3枚に絞る=自己決定のトレーニング
この作業が何より重要です。
なぜなら、自分にとって「何が大切だったか」を、
言語化する準備が整うからです。
さらにこのプロセスは、
自己肯定感の土台である「自己決定感」を育てることにもつながります。
🧠 実践して感じたこと(筆者体験)
正直、最初は「3枚なんて無理…!」と思いました。
だって、いい言葉は10個も20個もあるし、
全部が大事に見えるから。
でも、あえて“選ぶ”ことでわかったのは──
✔️ 「一番心が動いたのは、結局この3つだったんだな」
✔️ 「この言葉が、いまの自分には必要だったんだな」
ということでした。
読むことが、いつの間にか“選ぶこと”になり、
“残すこと”になり、
“自分の人生に持ち帰ること”になる──
読書の質が、1段階深くなった気がします。
✅ 付箋3枚ルール・手順まとめ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 各章を読了後、1ページだけに付箋を貼る | → 「章のなかで一番刺さったページ」 |
| ② 全章で付箋を貼り終える | → たとえば6章なら6枚 |
| ③ その中から3枚に厳選する | →「いまの自分にとって一番大切な3つ」 |
──この作業が終わった頃には、
「もうこの本、自分のものになったな」と感じるはずです。
電車の中で出会った「たくさんの付箋」
この記事を書いている朝、
通勤電車で読書をしている女性を見かけました。
その本には、びっしりと色とりどりの付箋が貼られていて、
まるで本そのものが“会話の相手”になっているようでした。
アバタロー式では「3枚に絞る」ことを推奨しています。
けれど、あの付箋だらけの本を見て、私は思いました。
たくさん貼るのも、きっとその人にとっては大切な“記録”なのだと。
絞ることも、残すことも、どちらも“自分との対話”。
大事なのは、どう読むかより、どう残るか──
そんな気づきをもらった朝でした。
インプット術×読書環境の整え方:“読むだけで終わらない読書”を支える仕組みづくり

読書術というと「どうアウトプットするか」が注目されがちですが、実は「どうインプットするか」も同じくらい大切です。
本書『自己肯定感を上げる OUTPUT読書術』では、アバタローさん自身が日々意識している
「読書環境の整え方」
「本との付き合い方」
が丁寧に綴られており、
特に以下の2点は、読書に苦手意識がある方にも刺さるヒントになっています。
本とネット、どう使い分ける?
私たちは今、あらゆる情報にアクセスできる時代に生きています。
でもそれだけに、「何をどこで学ぶか」を見極める力が問われています。
アバタローさんが推奨するのは、次のようなシンプルな使い分け:
本 → 情報を“体系的に”学びたいとき
→ たとえば「自己肯定感とは何か?」を深く学ぶときネット → 情報を“断片的に”調べたいとき
→ たとえば「自己肯定感が下がっているサインとは?」など今すぐ知りたいとき
これを意識するだけで、読書の満足度も記憶の定着率もぐっと高まります。
難解な本を読むための「3冊戦略」
哲学や経済、心理学などの専門書を読もうとしたとき、
「何を書いてるかまったく分からん……」
そんな挫折経験、ありませんか?
でもそれは、あなたの理解力の問題ではありません。
“橋渡し役”の本を読んでいないだけなんです。
アバタローさんが紹介していたのは、難解なテーマに出会ったときの「3冊戦略」。
| 種類 | 目的 | 例 |
|---|---|---|
| ① 全体構造がわかる本 | 図解・超初心者向けで全体像を把握 | 図解○○入門、漫画でわかるシリーズ |
| ② 文章がわかりやすい本 | 平易な文章で理解を深める | 新書・会話形式の入門書 |
| ③ 詳細がわかる本 | 辞書的に使える、専門性の高い本 | 原典・アカデミックな専門書 |
たとえば「哲学に興味がある」となったら、いきなりカントやニーチェに突撃するのではなく──
漫画で概要をつかむ
わかりやすい対話本で補強する
興味が深まった部分だけ専門書で調べる
という順番で進めるだけで、理解度と読了率が一気に上がります。
一時期、図解入門系の本ばかり読み漁っていましたが、これは本当におすすめです!
これだけで、わかった気になってはいけませんが理解はできるみたいなレベルになります。
環境が変われば、読書はもっと楽になる
集中できる空間づくりも、インプットの質を左右します。
私が特に実感したのは「スマホとの距離感」です。
読書前にスマホを裏返しておくだけで、集中力が全然違う。
アバタローさんは「読書の前にスマホを隠す」という環境づくりを最初のステップにしています。
そのささやかな習慣が、読書=集中できる体験として脳に記憶され、
徐々に“読書体質”へと自分を変えてくれるのです。
読書に「才能」なんていらない
難しい本を読めないのは、才能や知識がないからじゃない。
ただ、設計図がなかっただけ。
「本で学びたいけど、何から始めたらいいか分からない」
「読みたいけど途中で挫折してしまう」
そんな方にこそ、この章のインプット術は届いてほしいなと思います。
焦らず、自分のペースで読書を“積み重ねる設計”を持ちましょう。
まとめ|読書は「自信の土台」になる
本を読むという行為は、知識を得るためだけのものではありません。
読書は「自己信頼」を育てるための習慣であり、
それを可能にするのが「アウトプット」という行為でした。
本書から学んだ5つのキーワード:
比較しないで、自分の歩幅で読む(原則)
→ フォロワー数でもPV数でもなく、「昨日の自分」と比べよう。読書は対話(ツッコミモード)
→ 問い・主張・根拠を拾って、自分の思考を鍛える時間に。3枚の付箋で、記憶と自信を残す
→ 自分の「大切」を選ぶ力=自己決定感が育つ。本とネットは、目的別に使い分ける
→ 本=体系化、ネット=補完。どちらも“味方”に。難しい本には、段階を踏んで挑む
→ 図解・入門・辞書型の3冊で挫折を回避しよう。
この本が教えてくれたのは、
「読書とは、知識を得ることではなく、自分を知って育てていくプロセスである」
ということでした。
きっと、1冊の本のなかに“人生を変える問い”が隠れている。
その問いと向き合いながら、少しずつ自分を知っていけたら──
きっと読書は、自分と仲良くなるための習慣になっていくはずです。
🔖最後に
読書メモをとって、ブログにまとめてみる。
感想をSNSに書いてみる。
たったそれだけで、読書の世界はグッと深く、長く、あたたかいものになります。
今日から、あなたなりの「OUTPUT読書」を始めてみてくださいね。


