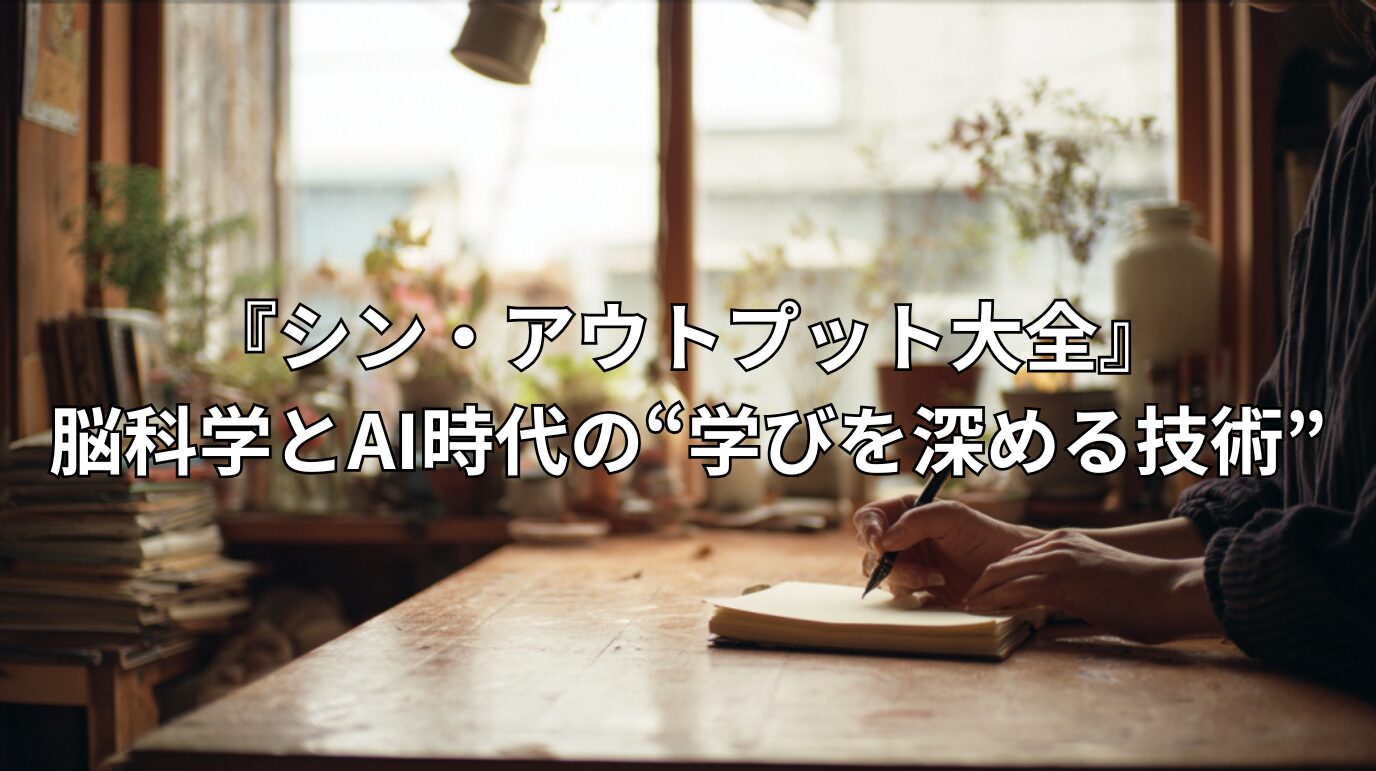目次
耳読書で人生が変わった話|通勤時間が“学びのゴールデンタイム”になった理由
耳読書で、人生が静かに変わり始めた
家を出て、駅まで歩く。
電車に揺られて、会社へ向かう。
毎日1時間ほどかかるこの通勤時間が、僕にとっての「人生を変えた読書時間」になった。
耳読書──つまり、本を“目で読む”のではなく、“耳で聴く”というスタイルに切り替えてから、世界の見え方が変わった。
これまでは、スマホをぼんやり眺めているうちに駅に着くのが日常だった。SNSを流し見して、音楽を流して、あるいはゲームに没頭して。
本を読もうにも、満員電車でページをめくるのは気が散るし、正直しんどい。
でも、オーディオブックを使い始めてから、状況が一変した。
スマホにイヤホンをつなぐだけで、どこにいても読書ができる。
歩きながらでも、混雑の中でも、本が“自分の中に入ってくる”感覚がある。
往復で2時間──これが、「インプット」と「思考」のためだけに使える時間になったことは、僕の中で大きなブレイクスルーだった。
通勤時間を「耳の読書習慣」に変えるだけで、思考が進化する
朝、仕事に関する本を聴きながら出社すると、自然と頭の中で“今日やるべきこと”の優先順位が整理されていく。
たとえば営業力を高めたいときは、営業に特化した音声教材やノウハウ本を。
新規事業の立ち上げ期には、それに関連するビジネス書だけを選んで毎朝流していた。
今の自分に必要な知識を、最も効率よく取り込める手段。
それが、僕にとっての耳読書だった。
「ロジカルシンキングを学びたい」と思ったときも、キーワード検索から関連書籍を見つけて、数冊を一気に耳で“読破”。
読むというより、“浴びる”に近い感覚。気づけば自然と、日々の会話や資料作成の中で論理が整理されていることに気づいた。
そして最近では、アウトプットも意識するようになった。
読んだ(聴いた)本は、メモに残したり、このブログやnoteで感想を書いたりする。
「情報を自分の言葉で語る」ことが、知識を定着させる一番の方法だということを、ようやく実感できるようになってきた。
耳読書って、ただの“時短”じゃない
「耳で聴く読書」と聞くと、
「ながら作業用のBGM的なものでしょ?」
「紙の本に比べて、内容が頭に残らないんじゃない?」
そんな声もよく聞きますし、僕も最初はそう思っていた。
でも実は、耳読書には“科学的にも”しっかりとした裏づけがある。
単なる「時短術」や「お手軽インプット」ではなく、
脳の使い方そのものを最適化する手段と言っても過言ではない。
「物語理解」は、紙でも音声でもほぼ同じ
近年の研究によれば、小説や物語といったナラティブ型のコンテンツに関しては、
耳で聴く場合と、紙で読む場合で理解度に大きな差はないということが分かってきている。
たとえばスタンフォード大学の実験では、
参加者に同じ内容の物語を「紙で読むグループ」と「耳で聴くグループ」に分けて比較。
両者の記憶保持率や感情の共鳴度は、ほぼ同等という結果が出た。
つまり、「物語や実例で学ぶ系の本(自己啓発・ビジネス書・エッセイなど)」は、
耳からでも“ちゃんと入る”し、深く残る。
歩くリズムが、脳を覚醒させる「ムーブ×学習」
僕自身も実感しているが、
「歩きながら聴く」スタイルは、思っている以上に脳が冴える。
実際、リズム運動(歩行・軽いジョギング)をしながらの音声学習は、前頭前皮質の活性化を促すという研究もあり、
アイデア発想・創造性・記憶力に良い影響を与えることが分かっている。
歩行中にふとメモしたくなるような「ひらめき」や「自分ごとの気づき」も、
実は脳科学的にはしっかり説明がつく現象なのだ。
読書習慣がつかない人こそ「耳」から始めよう
本を読む習慣がなかなか身につかない──
そんな悩みを持つ人にも、耳読書は抜群の相性を発揮する。
なぜなら耳読書には、
目の疲れがない
ながら聴きができる
内容に引き込まれやすい
定着しやすい(再生スピードや繰り返しに最適)
といった強みがあり、
さらに最近では発達障害やディスレクシア(読み書き困難)を抱える人にとっても「読書の入り口」として活用されている。
僕も「紙で読むほど集中できない時期」があったが、
耳からの読書が“知的なリハビリ”のように思考力を取り戻してくれた感覚がある。
耳読書は、ただの“手抜き”でも“代替手段”でもない。
脳と習慣に合った「別の入り口」。
むしろ、今の時代にぴったりフィットする新しい読書体験だと感じている。
次章では、そんな耳読書をどうやって日常に取り入れるか?
僕自身が続けられた「3つの習慣化ワザ」を紹介していきたい。
僕がやってる「耳読書×3つの習慣化ワザ」

耳読書をただ“聴いて終わり”にしないために、僕が大切にしているのは「習慣に組み込むこと」だ。
いくら内容が良くても、1回聴いただけでは日常に活かしきれない。
だからこそ、「どのタイミングで、どんなふうに耳読書を取り入れるか」がカギになる。
以下は、僕が実際にやって効果を感じている3つの習慣化テクニックだ。
① 歩きながら聴く:「感情が動いた瞬間」をメモに残す
朝の駅までの道、会社からの帰り道。
歩いている時間は、耳読書の“ゴールデンタイム”だ。
ただ流し聴きするだけではもったいない。
僕は、聴いている途中で「おっ」と心が反応した言葉やフレーズがあれば、スマホのメモアプリに一言だけメモを残すようにしている。
たとえば──
「これは自分に必要な問いかけだな」
「この考え方、あの仕事に活かせるかも」
といった、“自分ごと化”された気づきを拾っていく。
そうすると、ただの音情報が「行動に結びつくヒント」に変わってくるのだ。
② 電車で聴く:固定化した“再生リスト”で脳を自動起動
電車に乗るときも耳読書をしているが、ポイントは“選書の迷い”をなくすこと。
前日の夜に「明日の通勤で聴くリスト」を決めておき、
SpotifyやAudibleのプレイリストに登録しておく。
これを続けていると、
「〇〇駅を過ぎたらこの章に入る」
「この景色を見ながらこの話を聴いた」
といった、ルーティン化×記憶のアンカー効果が起こってくる。
つまり、電車に乗る→イヤホンをつける→“勝手に脳が学習モードに入る”
という流れができてしまうのだ。習慣に勝る意志力はない。
③ noteで書く:48時間以内に“自分の言葉”でアウトプット
インプットした内容を定着させるには、「聴いたら書く」ことが効果的だ。
僕は、耳で読んだ本を48時間以内にnoteやブログで文章化するようにしている。
すべてを書き起こす必要はない。
心に残ったポイントを3つ程度に絞って、自分の言葉で語ってみる。
この“自分の言葉にする”というプロセスが、
情報を「わかったつもり」から「使える知識」へと変えてくれる。
実際、この習慣を始めてから
「話の切り出し方」や「伝える言葉選び」が変わったと感じる場面も増えてきた。
耳読書は、それ単体でも価値があるけれど、
日々の生活リズムと掛け合わせていくことで、想像以上の成果を生み出す。
音声学習に向いてるジャンル/向いてないジャンル
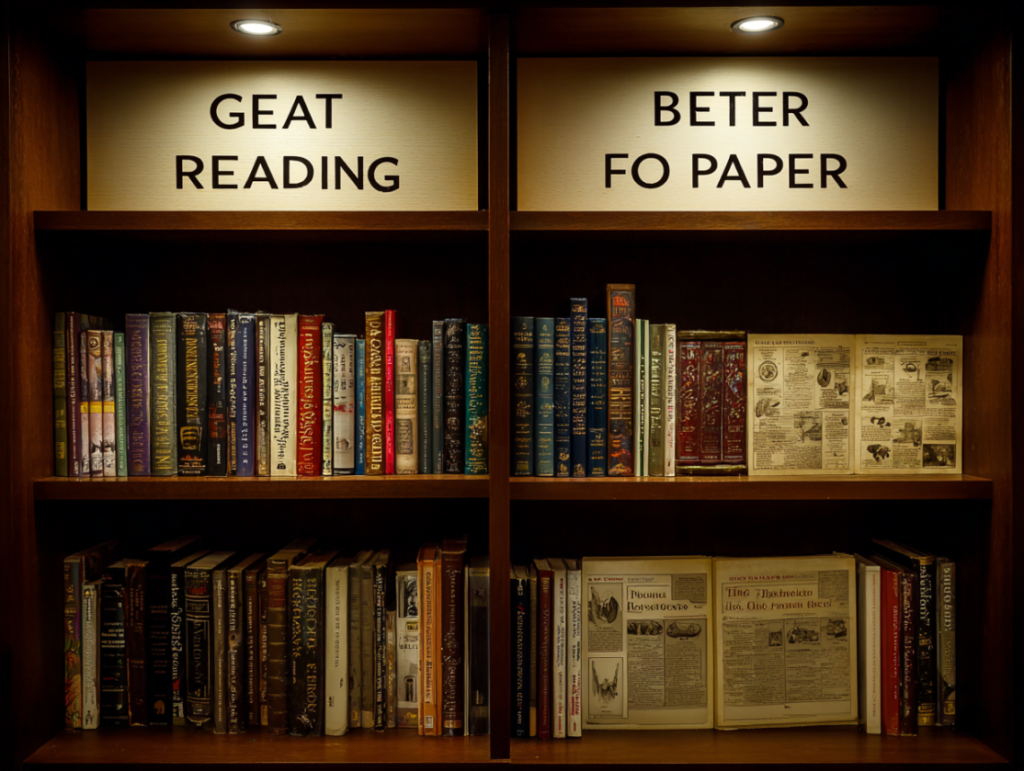
耳読書のメリットは大きいが、すべての本が音声で“読める”わけではない。
実際に様々なジャンルを耳で聴いてきた中で、「向き・不向き」は確実に存在すると感じている。
ここでは、音声学習においてどんな本が効果的か/どんな本は工夫が必要かを整理しておきたい。
◎ 向いているジャンル|「ストーリー・会話・実践系」
以下のようなジャンルは、耳読書との相性が非常に良い。
小説・物語(特に1人称)
登場人物の声や語りが耳に入りやすく、感情移入しやすい。
物語構造が脳内に映像として展開されやすく、没入感が高まる。自己啓発書・ビジネス書(実例ベース)
「物語+実践」の形式をとる本は耳からの理解が進みやすい。
音声で繰り返し聴くことで、マインドセットの浸透にもつながる。対談・インタビュー・エッセイ
話し言葉に近い文体は音声との親和性が高い。
読むよりも「語られている内容」として自然に受け取れる。
これらのジャンルは、紙で読んだときよりも“親密さ”や“記憶の定着”が高くなることも多い。
△ 工夫が必要なジャンル|「図・構造・抽象度が高い本」
一方で、以下のようなジャンルは注意が必要だ。
図表が中心の実用書・技術書
図の説明だけが音声で流れても理解が追いつかず、全体像がつかみにくい。
付属のPDFなど付いているが、最大のメリットである「ながら」が出来ない。ロジックの階層構造が深い本(哲学書・論文系)
A → B → C → Dというように段階的に積み上げていく本は、
一度でも聴き逃すと論理の流れが崩れてしまうことがある。記号や計算が頻出する専門書
数学・プログラミング・法律条文のような“目で見る情報”が多いジャンルは、
基本的に紙の方が圧倒的に適している。
こうした本を耳で学びたい場合は、「ダブル読書」=耳+紙の併用がおすすめだ。
◎ 耳読書を“補完”するツールたち
音声学習の弱点を補う手段として、僕自身が活用しているのが以下のようなツール群だ。
GPTによる要約(章ごとの理解を確認)
聴いた直後にChatGPTなどで「この本の第3章を要約して」と投げるだけで、記憶の定着が格段に高まる。章ごとのハイライトメモ(Notion/Googleドキュメントなど)
「あとで振り返れる場所」があると安心できるし、アウトプットの下地にもなる。再生速度の調整(1.25~1.5倍が基本)
内容が複雑な本はあえて1.0倍に戻すなど、“耳の負荷”を調整するのもひとつの工夫だ。
要は、「耳だけで完結しようとしない」こと。
耳を入り口にして、紙やツールと連携させることで、音声学習の効果は何倍にも跳ね上がる。
Q&Aで「耳読書はじめて」の疑問を解消!

耳読書を始めようと思ったとき、誰もが一度は感じる疑問や不安がある。
ここでは、僕自身が実際に試してきた中でよく聞かれる質問と、その答えをQ&A形式でまとめてみた。
Q1|再生速度はどれくらいがいい?
基本的には 1.25〜1.5倍 がちょうどいい。
人間の脳は、日常会話よりもやや速いスピードで話される内容の方が集中しやすいと言われている。
最初は1.0倍で聴いて、慣れてきたら徐々に速度を上げていくのが王道。
逆に、論理の階層が深い本や、初めて触れる分野の本は1.0倍でじっくり聴くのがおすすめだ。
再生アプリによっては「1.2倍」や「1.4倍」など細かい調整ができるので、
自分の集中力と内容の難易度に応じて最適なスピードを見つけるといい。
慣れてくれば2倍速でも聴くことは可能!
Q2|“聞き流し”でも効果はあるのか?
結論から言えば、「ながら聴き」でも効果はあるが、“意識のモード”がカギになる。
耳読書には「注意モード」と「非注意モード」がある。
注意モード: 意識的に内容を理解しようとしている状態。記憶定着・行動変容につながりやすい。
非注意モード: BGM感覚で流している状態。感情や雰囲気だけがうっすら残る。
もちろん、すべてを注意モードで聴くのは難しい。
でも、1つでも「お、これは…」と思えるフレーズが刺さったら、それだけで意味がある。
ポイントは、刺さった瞬間を見逃さず、メモやマーカーで「残す」ことだ。
Q3|寝る前に耳読書しても大丈夫?
寝る前の耳読書は、入眠儀式としては◎、記憶定着としては△といった位置づけになる。
音声によってリラックスできるのは確かだが、
脳が「情報を処理して覚える」フェーズには入りにくいため、内容の定着という意味では効果が薄い。
特に自己啓発書やビジネス書を寝る前に聴くと、思考が活性化してしまい、かえって眠れなくなることもある。
おすすめは以下のような活用法だ:
小説やエッセイなど“心地よいストーリー系”を寝る前に聴く
必ずスリープタイマー(15〜30分)を設定する
途中で寝落ちしてもOKな内容にする(再聴しても楽しめるもの)
眠る前は“記憶のため”ではなく、“心を整えるため”の耳読書として使うのがベストだ。
耳読書は、気軽に始められる分、つまずきポイントも人それぞれ違う。
でもこうした疑問をひとつずつ解消していけば、自分に合った“耳の学びスタイル”が必ず見つかるはずだ。
次章では、今日から始められる耳読書の「3ステップ実践法」を紹介していく。
ここまで読んでくれたあなたに、明日の朝からできる小さな行動のヒントを届けたい。
今日からできる「耳読書」スタート3ステップ

耳読書に興味を持っても、「実際にどう始めたらいいのか分からない」という声は多い。
でも、始め方は驚くほどシンプルだ。
ここでは、今日から誰でも実践できる3つのステップを紹介する。
この3つさえ押さえておけば、「耳読書」がただの思いつきで終わらず、日々の習慣に変わっていくはずだ。
① 聴く時間を“固定習慣”に乗せる
耳読書は、「何かをしながら」が基本スタイルだ。
だからこそ、すでに日常にある習慣の“上にのせる”のがもっとも続きやすい。
おすすめは以下のようなタイミング:
通勤・通学の電車や徒歩時間
朝の支度・歯磨き中
夜の軽い運動や家事(洗濯・食器洗いなど)
「この時間になったらイヤホンをつける」
というトリガーさえ決めてしまえば、考えなくても始められる状態ができる。
② 聴く本を前夜に選ぶ
意外と見落としがちなのが、「何を聴くかで迷う時間」だ。
この迷いがあるだけで、行動のハードルは一気に上がる。
だからこそ、前日のうちに1冊(もしくは1章)だけ決めておくのがいい。
SpotifyやAudibleなどのプレイリストにあらかじめ登録しておけば、
朝起きて再生ボタンを押すだけで、自然に耳読書がスタートする。
小さな準備こそが、習慣化の最大の武器になる。
③ メモ or 3行要約でアウトプット
最後に、聴いた内容を「残す」ことも忘れてはいけない。
すべてを覚える必要はない。
でも、自分の中に少しでも残しておくことで、読書が記憶に変わっていく。
おすすめはこの2つの方法:
スマホのメモアプリに1行だけ印象的な言葉を書く
3行程度で「この本で印象に残ったこと」をまとめる
それを日記に書いてもいいし、SNSでシェアしてもいい。
アウトプットすることで、自分の中に“言葉として定着する体験”が生まれる。
耳で読む。行動につなげる。
それだけで、日々の景色は少しずつ変わっていく。
今日から始められる。
イヤホンひとつと、ほんの少しの好奇心があれば、誰にでもできる。
あとは、続けていくだけだ。
耳読書は、“小さな革命”になる
耳読書は、読書のあり方を変えるだけではない。
時間の使い方を変え、習慣を変え、思考の質そのものを変えてくれる。
僕自身、最初からAudibleに手を出したわけではなかった。
むしろ、「活字を読むのがしんどい」と感じていた時期に、
YouTubeで本を要約してくれるチャンネルを見つけたのがすべての始まりだった。
通勤の途中に、たまたま流した1本の要約動画。
それが、自分の中のスイッチを押してくれた。
「読書って、こんなに気軽でいいんだ」
「“耳で聴く”って、むしろ今の自分には合っているかも」
そんな感覚が芽生えたところから、耳読書の旅が始まった。
だから、もし今「本を読むのが苦手」と感じているなら、
いきなりオーディオブックを買う必要はない。
まずは、要約動画や読み聞かせチャンネルを“聴いてみる”ことから始めてみてほしい。
大切なのは、自分に合った入口を見つけることだ。
耳から入った言葉が、いつか心の奥深くに残るかもしれない。
そして気づいたときには、行動も考え方も変わっている──そんなことが、実際に起こる。
耳で読むという選択肢は、誰にでも開かれている。
今日、あなたがイヤホンをつけるその瞬間から、
「学び」と「日常」が、静かにつながっていく。
Kindle Unlimited・Audible・flyer の比較表
読書をお得に楽しむ方法!
「本を読む時間がない…」「買う前に内容を知りたい…」
そんなあなたには 3つの選択肢 があります!
Kindle Unlimited なら 月額980円で200万冊以上が読み放題!
Audible なら プロのナレーションで耳から学べる!
flyer なら 10分で本の要点をサクッと理解!
Kindle Unlimited・Audible・flyer 比較表
| サービス | 特徴 | 無料体験 | 料金 |
|---|---|---|---|
| Kindle Unlimited | 200万冊以上が読み放題 | 30日間無料 | 月額¥980 |
| Audible | プロの朗読で耳から読書 | 30日間無料 | 月額¥1,500 |
| flyer | 10分で本の要点を学べる | 7日間無料 | 月額¥550〜 |
どれが自分に合う?選び方のポイント!
じっくり読みたいなら →Kindle Unlimite
スキマ時間に聴きたいなら →Audible
要点だけサクッと知りたいなら →flyer