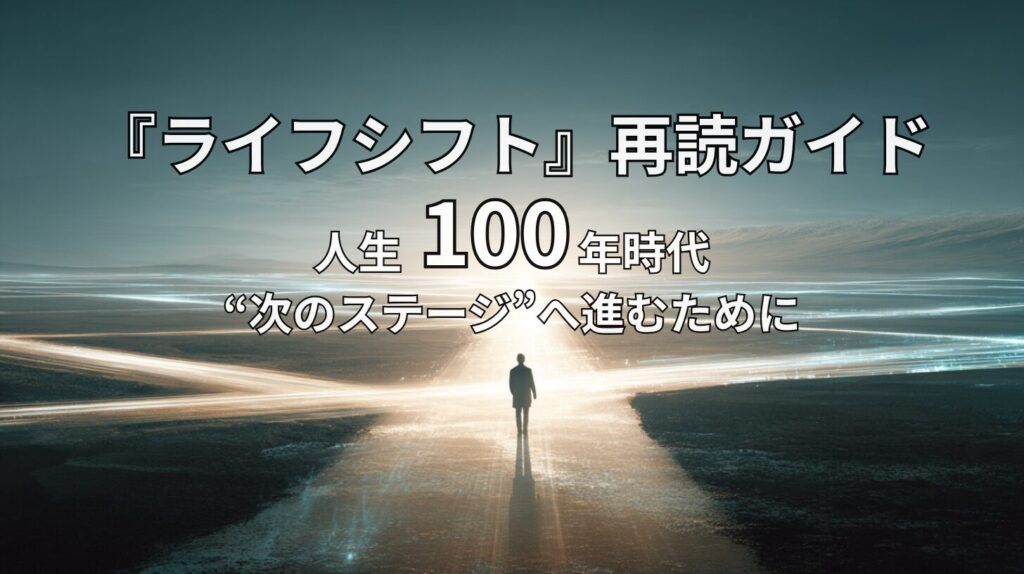
目次
人生が「こんなに長いなんて、聞いてない」
もしもあなたの人生が、あと60年も残っているとしたら──
それは、嬉しいことですか?
それとも、ちょっと困りますか?
多くの人が口にしないけれど、心の奥で感じていることがある。
「こんなに長く生きるなんて、誰も教えてくれなかった」と。
20代まで教育を受けて、
60歳くらいまで働いて、
あとは“のんびり老後”を送る——
そんな“三段ロケットの人生設計”を信じて、
私たちは大人になってきた。
学校も、企業も、社会の制度も、全部がそうだった。
でも今、それではもう足りない。
人生100年時代なんて言葉は聞き飽きたけれど、
現実は、もうそこにある。
2025年、日本の平均寿命は男性81.09歳・女性87.14歳。
国民の10人に1人が、80歳以上。
もっと言えば、70歳は“もう老後”ではなく、“まだ現役”かもしれない。
けれど私たちの働き方も、お金の使い方も、「いつか終わる前提」で設計されている。
たとえば60歳までに住宅ローンを終わらせるとか、
65歳から年金で暮らすとか、
そのあと30年も“なんとかする”だけの人生なんて、
本当は怖くて想像したくない。
そんな時代に登場したのが、
『LIFE SHIFT──100年時代の人生戦略』という本だった。
9年も前からこの本では、「寿命が伸びる」という現象を
“老いが長くなる”とはまったく違う角度から捉えていた。
「時間が伸びる」=「チャンスが増える」
問題は、その“増えた時間”をどう設計し直すかだ。
それはつまり、
これまでの「教育→仕事→引退」という一本道のレールを、
“複線化”し、自分で選び直していく人生。
学び直す人生、やり直す人生、つながり直す人生。
何歳であっても、新しく始められるという前提で生きるということだ。
でも、これはきれいごとではない。
現実に長寿の“歪み”と向き合ってきた私にはわかる。
介護現場で感じた違和感、高齢者の“閉じた老い”と、“開かれた老い”の差。
だからこそ思う。
人生が長くなった時代に必要なのは、終わりの設計ではなく、次のスタートの描き方だ。
👉 あなたの“人生設計図”は、いま、どこで止まっていますか?
そして、それを更新する準備はできていますか?
Three-Stage → Multi-Stage Life:「一本道」の人生は、もう存在しない

20世紀までの人生は、ある意味で“シンプル”だった。
前述したような「教育→就労→引退」という三段ロケットのモデル——
まるで決められたレールのように、ほとんどの人が同じ順序で人生を進み、
60歳で仕事を終え、老後の時間をのんびり過ごす。
でも、そのレールはすでに崩れかけている。
平均寿命が80歳を超え、90代まで現役で活躍する人も当たり前になった今、
その“決まった順番”では、もはや人生が持たない。
著者のアンドリュー・スコットは、寿命の延びを「中年期の拡大」と捉える。
たとえば、1世代ごとに6〜9年ずつ長く生きられるようになっているなら、
もはや私たちは、「老いを遅らせる」のではなく、人生そのものを拡張して再設計しなければならない。
これが、本書の最重要概念のひとつ——
「Three-Stage Life」から「Multi-Stage Life(マルチステージ)」への転換である。
マルチステージの人生とは、
キャリアの途中で何度も立ち止まり、
学び直し、働き方を変え、価値観さえ更新しながら、
「自分だけのステージ構成」を柔軟に描いていくということ。
就職→転職→学び直し→副業→起業→パート勤務→介護→再チャレンジ…
かつては“例外”だったこのような人生の流れが、
いまや“標準”になりつつある。
この変化は、働き方にとどまらない。
たとえば、「退職」という概念も変わりつつある。
スコットは、退職とは“完全に辞める”のではなく、働き方の再設計だと語る。
週3勤務、プロボノ活動、メンター職…
段階的・流動的な引退というライフスタイルが、新しい標準になってきている。
※プロボノとはについて、サービスグラント様の記事を置いておきます。
マルチステージ化した人生では、もはや「正解のルート」は存在しない。
あるのは、*試しながら作っていく人生”だけだ。
そしてそこには、従来の「年齢=役割」という考え方が通用しない。
30歳で学び直してもいい。
50歳でキャリアチェンジしてもいい。
70歳で仕事を続けてもいい。
重要なのは、「何歳か」ではなく「何を選ぶか」なのだ。
今、私たちが問い直すべきなのは、
「いつまで働くか」ではなく、
「何度、生き直すか」なのかもしれない。
“無形資産”が、人生のLTV(生涯価値)を決める時代へ

「お金さえあればなんとかなる」
——その前提は、人生100年時代では通用しない。
『LIFE SHIFT』が世界中で注目された理由のひとつが、
「これからの時代、お金よりも“無形資産”が重要になる」という提言だった。
多くの人が資産といえば「貯金」「保険」「不動産」など、有形のものを思い浮かべる。
しかし、人生が長くなるにつれて、必要なのは“数値化できない資産”の質とバランスだと、
著者たちは主張する。
◆ 無形資産=人生を支える3つの“見えない力”
① 生産性資産
→ スキル・知識・仕事における生産性を高める力
例:専門性、タイムマネジメント、リーダーシップ、AIリテラシーなど
2025年時点では、「人+AI」の共存力(プロンプト力/対話力)が鍵
キャリアが長くなるほど、“どこでも通用するスキル”が武器になる
② 活力資産
→ 身体的・精神的な健康、人間関係の質
例:運動習慣、食生活、睡眠、人とのつながり
ポストコロナの今、“健康格差”が生涯年収に直結する時代
高齢期における孤立・不安・うつを防ぐ“コミュニティの質”も重要な資産に
③ 変身資産
→ 変化に適応し、人生のステージを“再設計できる力”
例:学び直し力、自己認識力、レジリエンス(回復力)、セルフリーダーシップ
「正解がない」キャリアの中で、“何度もやり直せる自分”を持てるかが分かれ目
この資産がないと、長寿はむしろ“迷子の時間”になりうる
著者たちはこう語る。
「人生のLTV(生涯価値)を高めるのは、金融資産ではない。
むしろ、“変化と共に更新できる能力”そのものが最大の資産だ」
◆ 無形資産は「自動的には貯まらない」
ここが重要だ。
無形資産は、有形資産のように“給与天引き”で貯まっていくわけではない。
生産性資産は、意識的な学習時間の確保と実践が必要
活力資産は、日々の習慣と人間関係のメンテナンスが必要
変身資産は、むしろ“挫折経験”や“越境経験”の中でしか育たない
つまり、放っておけば減っていくものなのだ。
🧭 2025年の再読ポイント
ChatGPTなどの登場により、スキルの半減期が短縮
→「何を学ぶか」より、「どう学び直せるか」が差になる介護の現場でも、変身資産の高いスタッフが現場を回している
→ 指示待ちではなく、自分の役割を“編み直せる人材”が求められているSNS時代の“つながり疲れ”と“健康格差”が活力資産の格差を広げている
人生100年時代を支える“3つの見えない力”。
それは、いわば「自分という人間のOS(オペレーティングシステム)」だ。
Jack / Jimmy / Jane──“もしも人生が100年続くなら”という問いのシミュレーション

「あなたがもし、100年生きるとしたら――その人生、どんな風に設計しますか?」
この問いに、3つの人生パターンで答えようとしたのが、Jack・Jimmy・Jane という架空のキャラクターたちです。
本書では、人生100年時代に直面するであろう3つの典型的な「ライフパターン」を通じて、無形資産の蓄積・分配・喪失がどのように人生を変えるかをシミュレーションしています。
2025年の今だからこそ、この3人の人生に私たちはもっとリアルな“自分事”として向き合えるようになりました。
◆ Jack|順調なキャリアを歩む「スキル資本主義」の勝者
学歴・スキル・年収・人的ネットワークに恵まれたエリートコース
若いうちから自己投資を続け、生産性資産・活力資産を着実に蓄積
キャリアの複線化や学び直しも恐れず、変身資産にも余裕がある
▶ 2025年版のJack像:
Generative AIを使いこなし、サイドプロジェクトも複数。
「会社に属する」よりも“自分がブランド”として生きる感覚を持っている。
キャリアは職位ではなく、「影響力」と「柔軟性」で評価。
◆ Jimmy|安定を得られない「分断されたキャリア」の象徴
学歴・職歴に恵まれず、非正規雇用でキャリアの軸が築けない
生産性資産を蓄積する機会が限られ、活力資産も脆弱
変化を乗りこなす“変身資産”も持ち合わせず、長寿が「不安の時間」になる
▶ 2025年版のJimmy像:
フリーター・単発派遣・配達員など、スキルの再蓄積が難しい働き方が続く。
しかし近年では、「副業からのスキル再起動」や「生成AIでの越境学習」によって、
“再スタートの扉”が開き始めている人たちもいる。
Jimmyは、“放置されれば格差の象徴”になるが、
支援とリスキリング次第で「遅れて咲く変身者」にもなり得る。
◆ Jane|意志ある越境者。「ライフシフト」の実践者
キャリアの途中で大きな転換を選び、学び直し・働き方の再定義を経験
3つの無形資産をバランスよく鍛え、「自分にとっての豊かさ」を再設計していく
長寿社会の不確実性を恐れず、「変化の中にいること」そのものを選んだ人
▶ 2025年版のJane像:
40代で離職後、介護の仕事に関わったことで人生観が一変。
AIやウェルビーイングと掛け合わせた事業を立ち上げるなど、
「人生の第3幕」を自ら創りにいく人。
Janeは、JackのようなエリートでもJimmyのような既存の被雇用者でもない。
むしろ、変化の“ど真ん中”を生きている存在であり、
人生100年時代の“再構築力”を体現するキャラクターだ。
◆ あなたは今、誰に近いですか?
この3人の物語は、単なる「類型」ではありません。
私たちは誰しも、Jackの時期もあれば、Jimmyのように迷う時期もあり、Janeのように転換を選ぶ時もある。
Jackのように順風満帆な時、無形資産を“貯める力”が試される
Jimmyのように苦しい時、周囲とつながる“変身のきっかけ”が鍵になる
Janeのように動き出す時、自分の中の“編集者”としての力が問われる
人生は「1人のキャラクター」では完結しない。
だからこそ、私たちは何度でも選び直せる。
何度でも、人生のストーリーを“書き換えられる”。
『LIFE SHIFT』の“再読”が必要な5つの理由
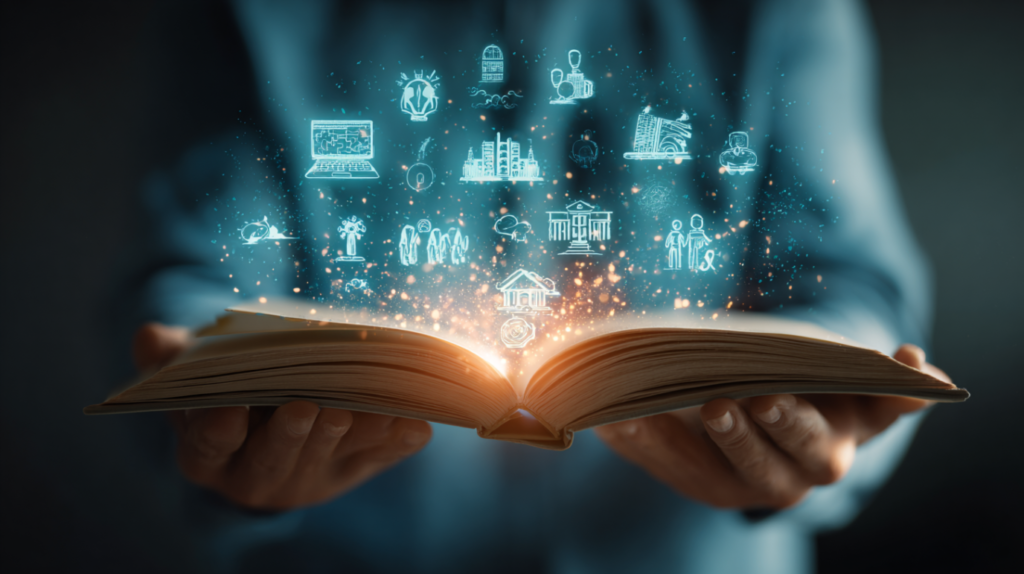
『LIFE SHIFT』が刊行されたのは2016年。
それから9年——私たちの働き方も、社会の仕組みも、大きく変わった。
そして2025年の今だからこそ、この本の“意味”も、また変わっている。
① AI の汎用化で「生産性資産」の陳腐化が早い
スキルを身につけても、数年で価値が下がる——
そんな時代がやってきた。
とくに生成AI(ChatGPTやClaudeなど)が登場してからは、
「覚えるより、組み合わせる力」のほうが圧倒的に求められている。
かつては“専門性”が強みだった仕事が、
いまやAIに補完・代替されつつある中、
“常に学び直せるかどうか”が、生産性資産の持続性を決める時代になるのだ。
② ポストコロナで「活力資産=ウェルビーイング」需要爆増
健康・睡眠・運動・人とのつながり。
これらが「贅沢」ではなく、“サバイバル資産”として再評価されている。
感染症の時代を経て、
人と会う、働く、学ぶ、遊ぶ——すべての体験において、
「どれだけ心と体が整っているか」が持続可能性に直結することを、私たちは体感した。
ウェルビーイング=“余裕”の象徴ではなく、
「人生を長く、豊かに走りきるための必須条件」に変わったのです。
③ 70歳雇用延長で“引退=解放”という神話が消滅
「60歳でリタイアして、のんびり余生を…」というイメージは、
もはや都市伝説に近いかもしれない。
企業の定年延長、政府の70歳就業推進、
そして“働く高齢者”の増加。
長く働くことは、選択ではなく“新しい前提”になりました。
だからこそ、
「働き続けたいかどうか」ではなく、
「どう働き続けられる状態をつくるか」が問われています。
④ 介護DXが「変身資産」の社会的価値を可視化
“変わり続けられる人”が、いま本当に必要とされている。
それを最も体感しているのが、介護・医療の現場である。
テクノロジー導入、制度改革、人材流動化——
現場では常に何かが変わり、
その変化に“ついていける人”だけが、
現場を支え、仕組みを動かしている。
「変身資産」は、もはや抽象的な言葉ではない。
実際に、社会を動かしている“行動の力”だ。
⑤ 最新作『ライフ・シフトの未来戦略』が“制度側の宿題”を提示
2025年には『LIFE SHIFT』の続編として、
『ライフ・シフトの未来戦略』(リンダ・グラットン著)が刊行されました。
この新作では、“個人の努力”だけでは限界があるという現実を見据え、
政府・企業・教育機関など「制度側」の設計課題が整理されています。
「制度をどう変えるか」と、「私たち一人ひとりが何を選び取るか」——
その両輪が揃って初めて、“100年時代”が可能性になる。
その意味でも、『LIFE SHIFT』を再読することで、
制度が動き出す“前夜”に必要な思考の土台を手に入れることができるのです。
アクションリスト|読後7日チャレンジ:あなたの無形資産を増やす1週間

人生を変えるのは、大きな決断よりも、小さな更新の積み重ね。
今日から始められる“7つの行動”で、あなた自身のライフシフトを始めてみませんか?
| Day | To-Do | 無形資産カテゴリ |
|---|---|---|
| Day 1 | キャリア100年年表を手書きする (10年ごとに“なりたい自分”を3つ書く) | 変身資産 |
| Day 2 | スキルの棚卸し+AI/介護の交点を検索してメモ | 生産性資産 |
| Day 3 | 毎朝10分、ストレッチ+瞑想を習慣にする | 活力資産 |
| Day 4 | LinkedInで世代の違う3人にDM・コメントしてみる | 変身資産 |
| Day 5 | NISAやiDeCoのシミュレーションを“90歳基準”で再設計 | 生産性資産 |
| Day 6 | ケアテックの施設見学・イベント・ボランティアを予約する | 活力資産 |
| Day 7 | 学び直し講座・セミナー・読書リストに1つ申し込む | 生産性資産 |
「100年ライフ」は、“長距離リレー”である
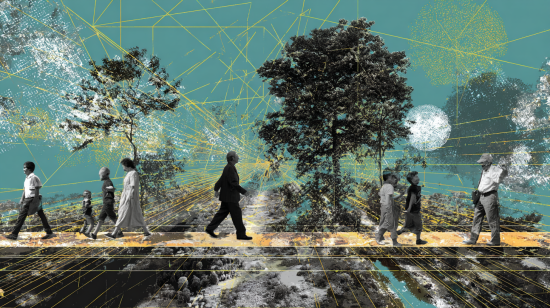
時間が伸びるということは、
ただ“老いる時間が増える”のではなく、
“可能性を渡し続ける時間”が増えるということ。
100年の人生を走りきるには、もはや“ひとりきり”では限界があります。
だからこそ――
個人は、無形資産を育てながら柔軟に走り続ける。
組織は、固定化された制度をほどき、選択肢をひらく。
社会は、学び直す文化と仕組みを共につくる。
『LIFE SHIFT』は、その“最初の設計図”です。
そして、2025年に登場した続編『ライフ・シフトの未来戦略』は、
制度・コミュニティ・働き方といった外側の「土台設計」を補完してくれます。
人生100年時代に、正解のキャリアやライフコースは存在しません。
あるのは、「何度でも変われる前提で、生きる覚悟」だけ。


