目次
“スクリーンの中に生きる”僕らへ

「ジョブズの子どもたちはiPadを使っていなかった」。
有名なこの話を聞いたときは誰もが少し戸惑う。
彼が世界に送り出した“魔法の板”は、実は家庭では制限されていたのだ。
TEDでアダム・オルターが語ったこの逸話は、
現代のテクノロジー産業に潜む大いなる矛盾を象徴している。
彼は「Dogfooding(自社製品を自分で使う)」というビジネスの慣習を紹介しながら、
こう問いかける――
なぜテック業界だけは、自分の作ったものを“家庭では使わない”のか?
スクリーンの裏には、「行動嗜癖(behavioral addiction)」のメカニズムが組み込まれている。
「依存症ビジネス」と呼ばれるこの構造は、
“あなたの時間”と“注意”を奪うために、
心理学とテクノロジーのすべてを結集して設計された。
本書『僕らはそれに抵抗できない』でオルターは、
SNSやゲーム、ストリーミングなどが人間の脳の「報酬回路」を狙い撃ちする仕組みを解き明かす。
人は意思が弱いのではない。
「やめ時のない設計」の中で生きているだけなのだ。
一方で、私たちは「モンクモード」という言葉をよく耳にする。
SNSを消し、スマホを遠ざけ、静寂の中で集中する“現代の修行”。
だが、その理想に到達できる人はごくわずかだ。
なぜなら、スクリーンの向こうには人間を離さない設計があるから。
通知音ひとつで脳が報酬を予期し、ドーパミンが放たれ、
また指が画面へと戻ってしまう。
オルターがTEDで見せた「24時間のグラフ」では、
睡眠や仕事、食事を除いた“白い時間”=自分の時間が、
スマホの赤い帯に少しずつ侵食されていく様子が映し出された。
その白は、創造し、対話し、夢を見るための時間。
彼は言う。
“That white space—that’s where your humanity lives.”
― その白い余白こそが、人間らしさの棲む場所だ。
モンクモードに入れないことを、
「意志が弱い」と責める必要はない。
それは、あなたが“設計された世界”の中で生きているからだ。
けれど、その構造を知り、
一瞬でもスクリーンの外に戻る勇気を持てば――
奪われた“白い時間”は、少しずつ取り戻せる。
奪われた“白い時間”

1日のうちで「自分の時間」はどれくらいあるだろうか。
睡眠と仕事、食事や身支度、家事や子育てを終えたあとに残る、ほんのわずかな余白。
その“白い時間”こそが、私たちの人間らしさの宿る場所だと、アダム・オルターは語る。
彼のTEDトークでは、24時間の円グラフが映し出される。
その中で、年を追うごとに白い部分が赤く塗りつぶされていく。
赤は、スクリーンの前で過ごす時間を示していた。
2007年――初代iPhoneが登場した年、赤はまだ小さかった。
しかし2015年には大きく膨らみ、私たちの自由時間の多くが画面の中へと吸い込まれていった。
オルターが示したのは、単なる統計ではない。
「注意」という資源が、静かに奪われていく過程だった。
彼は言う。
“That white space—that’s where your humanity lives.”
― その白い余白こそが、人間らしさの棲む場所だ。
『僕らはそれに抵抗できない』でも、
彼はこの「白い時間」を中心に語る。
SNSやゲーム、動画サービスが無料で使える理由――
それは私たちの“時間”そのものが商品だからだ。
「注意の経済(attention economy)」の中では、
あなたの視線が滞在すればするほど、誰かの収益が上がる。
だからこそ、アプリは「やめられない構造」で設計される。
終わりのないスクロール、次々に自動再生される動画、
“もっと見る”を押させる通知の仕掛け。
それらはすべて、あなたの白い時間を赤く染めるための導線だ。
気づけば、帰り道の数分、寝る前のひととき、
心を空にできるはずの時間が、
スクリーンの光に奪われている。
私たちは、他人の投稿やニュースの波を追いかけながら、
自分の内側と対話する時間を失っている。
そして、それに慣れてしまった。
モンクモード(デジタル断食)に挑戦しようとする人が多いのも、
本能的にこの“白い時間”を取り戻したいからだろう。
けれど、現代の生活では完全に離れることは難しい。
それは意志の弱さではなく、
「白を失わせる設計」の中に私たちが暮らしているからだ。
オルターの言葉は、単なる警告ではない。
それは「人間らしさを取り戻すための呼びかけ」だ。
失われた時間を、もう一度、白に戻すために――。
“やめ時”を奪う設計

私たちの「赤い時間」は、今もなお拡張を続けている。
通勤電車の中、信号待ち、寝る前の数分――。
気づけば指は、無意識のまま画面を滑っている。
ニュースを読み終えたはずが、下へ下へと流れる無限の情報。
YouTubeは次の動画を自動再生し、SNSは新しい投稿を永遠に供給する。
そこに「終わり」は存在しない。
TEDでアダム・オルターはこう語った。
“Stopping cues have disappeared.”
― 「止まる合図が、世界から消えた。」
かつてのメディアには、確かに“区切り”があった。
新聞は読み終えたら畳む、
テレビ番組はエンディングで一旦終わり、次の放送まで一週間待った。
その間に、私たちは思考し、会話し、記憶を整理する時間を持てた。
しかし今のメディアは、終わりを「設計的に」消している。
それは単なる便利さではなく、
あなたを離さないための構造だ。
変動報酬(Variable Reward)
この構造の中核にあるのが、
心理学でいう「変動報酬(Variable Reward)」という仕掛けである。
次に何が現れるか分からない――その“予測不能性”こそが、
人を最も強く惹きつける。
スロットマシンと同じ原理だ。
SNSの「いいね」や通知は、この不確実な報酬として設計されている。
次の瞬間、反応があるかもしれない。
もしかしたら、誰かが自分を見ているかもしれない。
その“かもしれない”が、ドーパミンを放ち続ける。
「あなたがスクロールを止められないのは、意志が弱いからではない。
それは“止まるための設計”が消されているからだ。」
――本書『僕らはそれに抵抗できない』のこの一節は、
いまや現代人全員へのメッセージだろう。
InstagramもTikTokも、終わりのない物語として作られている。
それは「次へ、次へ」と誘う無音の命令だ。
そして私たちは、気づかぬうちにその命令に従い続けている。
本来、ストッピング・キュー(やめ時の合図)は、
私たちが“現実に戻るための扉”だった。
しかしその扉が消えた今、
私たちはデジタルの廊下を永遠に歩き続けている。
それでも、完全に悪ではない。
問題は「設計」ではなく、
“止まることを取り戻せるかどうか”にある。
赤い時間を減らすことではなく、
“白い時間に戻る瞬間”を自ら設けること。
スクリーンが“幸福”を奪う瞬間
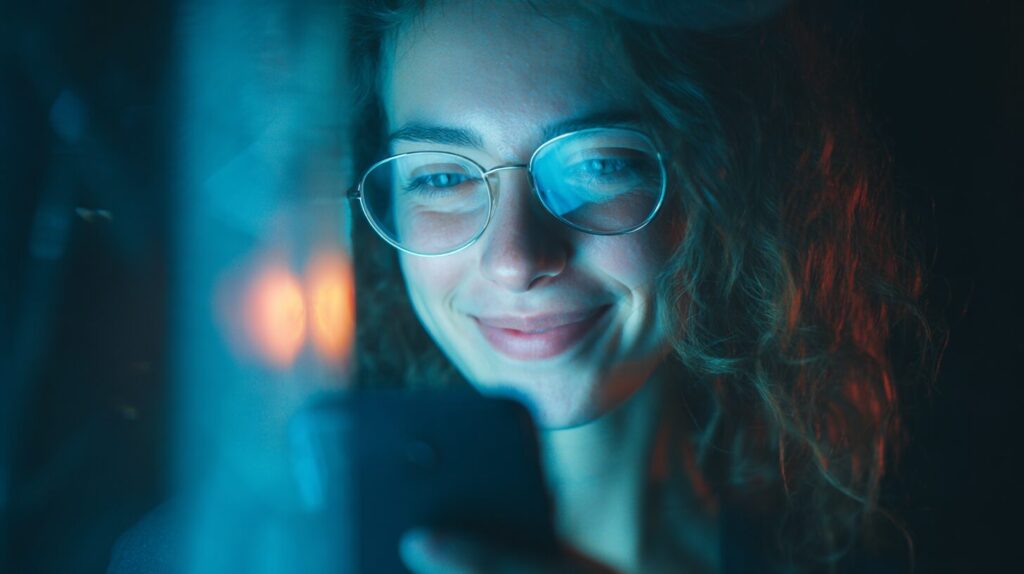
「好きなことをしているはずなのに、なぜか心が満たされない」
そんな感覚を覚えたことはないだろうか。
SNSを閉じたあとに残る、かすかな疲労。
動画を見終えたあとの、得体の知れない空虚。
それは、あなたが“間違った種類の快楽”を摂取しているサインかもしれない。
TEDでアダム・オルターは、
スマホアプリが私たちの幸福感に与える影響をデータで示している。
読書・運動・学習など、「自己を育てる系」のアプリを使っているとき、
人はおおむね穏やかで満足している。
その平均使用時間はわずか9分。
一方、SNS・ゲーム・ニュース・エンタメ――
脳を刺激する系のアプリに費やす時間は27分。
しかも、そのときの感情を問うと、
半数以上が「不幸だ」と答えるという。
“We spend three times longer on the apps that don’t make us happy.”
― 「私たちは、幸せを感じないアプリに3倍の時間を費やしている。」
私たちは、幸福をもたらさない行為に、
幸福を感じられる時間の3倍ものエネルギーを注いでいるのだ。
まるで、喉が渇いた人が海水を飲むように。
『僕らはそれに抵抗できない』では、
この矛盾を「報酬と快楽の錯覚」として描いている。
脳内のドーパミンは、喜びの物質ではなく“期待の化学物質”だという。
私たちは「次こそ楽しいはず」と期待しながらスクロールを続け、
その瞬間ごとの刺激に反応しているだけ。
満たされているようで、実は何も得ていない。
SNSで流れる笑顔や成功の瞬間を見て、
自分も何かを得た気になる。
けれど、それは他人の幸福の残像を浴びているに過ぎない。
その光に長く晒されるほど、自分の心の輪郭が薄れていく。
「ドーパミンの檻」という言葉がある。
私たちは、報酬の期待だけで動かされる脳の檻の中にいる。
そこでは“喜び”と“渇望”が入れ替わり、
刺激を与えないと落ち着かない。
一時的な高揚のあとに残るのは、静かな虚無だ。
それでも私たちは、
もう一度その檻の扉を自ら開け、指を動かす。
まるで自分の意思で選んでいるかのように。
けれど、その行動の多くは設計された選択だ。
「楽しい」と思うその瞬間、
誰かがあなたの時間を収益化している。
幸福とは、刺激の総量ではなく、
静けさの中で何を感じられるかにある。
だからこそ、スクリーンを閉じたあとに残る空虚は、
もしかすると、あなたの心が「本当の喜び」を探している証なのかもしれない。
“止まる”をデザインする

テクノロジーが悪いわけではない。
問題は、止まる設計が消えたことだ。
私たちは便利さの代わりに、余白を差し出してきた。
けれど、奪われたものを取り戻す方法は、意外と単純なのかもしれない。
TEDの中で、アダム・オルターは一枚の写真を紹介する。
あるオランダのデザイン会社では、午後6時になると――
天井に向かって机がゆっくりと上昇していく。
どんなに仕事が残っていても、
その時間になれば、オフィスの床は空になる。
4日間はヨガスタジオに、金曜日はダンスクラブに変わる。
つまり、物理的に“止まる”しかない仕組みが、会社そのものに組み込まれているのだ。
オルターは「自分の生活にも“停止ルール”を設計せよ」と提案する。
「5時から6時はスマホを触らない」といった時間指定より、
「食事のときは触らない」「寝室には持ち込まない」
といった行動の節目に紐づけるルールが効果的だという。
例えば、
食卓ではスマホを別の部屋に置く。
朝の1時間だけ、通知をオフにする。
週末は写真撮影以外の用途でスマホを使わない。
どれも小さなことだが、
その小さな“止まる習慣”が、やがて大きな静けさを連れてくる。
私たちは、脳に支配されているわけではない。
ドーパミンが指を動かすことはあっても、
どこで止まるかを決めるのは、いつだって自分だ。
その「意識的なブレーキ」を日常にデザインすることこそ、
テクノロジーとの健やかな共存の第一歩なのだ。
たとえば日本では、古くから“間(ま)”という文化がある。
会話の間、沈黙の間、呼吸の間。
そこに生まれる余白が、心を整える。
デジタル時代の「間」は、自分で設計しなければ生まれない。
だからこそ、
毎日一度でも“間”を取り戻す時間をつくることが、
新しい「デジタル禅」と言えるのかもしれない。
テクノロジーは、私たちを離さないように設計されている。
けれど、「止まる」をデザインすることは、まだ私たちの手に残されている。
それは戦いではなく、選択だ。
スクリーンの光を少し遠ざけて、
静かに呼吸を取り戻す――
それだけで、赤く染まった時間に、ほんの少し白が戻ってくる。
スクリーンの外で呼吸する

アダム・オルターのTEDは、一枚の風景で終わる。
アクセルを踏み込み、
スピードを上げ続ける車の中にいる現代人。
その手にはスマートフォン、
目の前には絶えず流れる情報の海。
そして彼は静かに言う。
“Leave your phone in the car.”
車を止め、海辺へ降り、
靴を脱いで、足を水に浸す。
風の音、砂の感触、波の冷たさ。
それらを感じることが、
「生きる」という行為の原点なのだと、
オルターは語りかける。
“Resist the pull(引き寄せに抗え)”。
オルターが本当に伝えたかったのは「戦うこと」ではない。
完全にデジタルを断つことでもない。
意識的に戻る時間を持つこと――
それが幸福の鍵だと彼は言う。
私たちの時間は奪われているようでいて、
奪い返す力も、また私たちの中にある。
それは一気に取り戻すものではなく、
日々の選択の積み重ねでしか取り戻せない。
スマホを置いて食事をする。
朝、空を見上げて深呼吸する。
たったそれだけのことが、
デジタルの波に沈みかけた心を岸辺へと戻してくれる。
テクノロジーはもはや切り離せない。
それでも、私たちはその中でどう呼吸するかを選べる。
スクリーンの光に照らされた顔の奥には、
まだ、自分の時間が息づいている。
「テクノロジーに負けない」よりも、
「人間らしさを取り戻す練習」として。
赤い時間の中に、
小さくても白い点を打つように――
今日という一日を、
自分の手で閉じてみよう。
その瞬間、
スクリーンの外に広がる世界が、
少しだけ色を取り戻す。
そしてあなたもまた、
ゆっくりと呼吸を取り戻すのだ。



