目次
動けない理由は“変化”だけではない

正直に言うと、初めて『チーズはどこに消えた?』を読み終えたとき、私は少し肩透かしを食らった気がしました。
外側の評価はあまりにも高く、「読むだけで人生が変わる」とまで言う人もいる。
だからこそ、ページをめくる手には期待がこもっていたのです。
けれど実際は――物語はあっけなく終わり、残ったのは「じゃあ、どうすればいいの?」という素朴な問いでした。
本書が示していることが間違っているわけではありません。
むしろ、変化に向き合う姿勢や恐れを手放す重要性は、その通りだと思います。
ただ、私の心が求めていたのは「考え方」ではなく「実際の一歩の踏み出し方」だったのかもしれません。
人生でも、変化が避けられないとわかっていても、足が止まる日があります。
そんなとき、多くの人が手に取る自己啓発の古典が、この『チーズはどこに消えた?』です。
1998年にアメリカで出版され、世界で累計2,800万部、日本でも400万部以上のベストセラーとなりました。
しかし、読んでみても「わかるけど動けない」という声は、私だけでなく少なくありません。
その空白を埋めるように2018年に登場した続編が『迷路の外には何がある?』(原題 Out of the Maze)。
動けなかった登場人物“ヘム”の視点で描かれた物語は、変化を受け入れるだけでなく、“思い込みを手放す”というもう一つの鍵を提示します。
今回は、この2冊をまとめて読み解き、変化の入口から出口までをつなぐ物語として書評していきます。
『チーズはどこに消えた?』――変化への初動を描く寓話

物語の舞台は、壁も天井もわからない迷路。
そこに暮らすのは、2匹のネズミ――スニッフとスカリー、そして2人の小人――ヘムとホー。
ある日、彼らの生活の中心だった“大量のチーズ”が忽然と姿を消します。
ここでいうチーズとは、出世、安定収入、愛情、健康、承認…私たちが心の底から求めているものの象徴です。
ネズミたちは、ほとんど迷わず新しいチーズを探しに走り出します。
一方、小人のヘムとホーは混乱し、その場から動こうとしません。
「これは間違いだ。誰かが元に戻してくれるはずだ」と信じ続け、日々不満を口にしながら、チーズが戻るのを待ちます。
やがてホーは、自分の恐れが“想像の産物”であることに気づきます。
そして壁にメッセージを書き残しながら、一歩ずつ迷路に踏み出し、再びチーズを見つける。
しかし、ヘムは最後まで動かないまま――物語は静かに幕を下ろします。
核心メッセージ
この物語が伝えたいのは、とてもシンプルです。
変化は避けられない
チーズは必ず動くし、時に突然消える。変化の兆しを嗅ぎ取れ
匂い=小さな変化を日常から察知する習慣が未来を左右する。恐れは小さな行動でしか消えない
頭の中で悩むより、まず動くことでしか不安は減らない。
この3つはどれも正論で、そして誰もが一度は耳にしたことがある考え方です。
しかし、その「当たり前」を寓話として短く、強く、印象づけてくるのがこの本の特徴です。
なぜベストセラーになったのか
1時間もあれば読める薄い本が、なぜここまで世界中で読まれたのか。理由はいくつもあります。
複雑さを捨てた寓話形式
心理学や経営理論を知らなくても理解できる。あらゆる場面に応用可能
仕事だけでなく、人間関係、健康、ライフスタイルなど、誰でも自分事として置き換えられる。時代背景とのシンクロ
1990年代後半、IT革命や終身雇用の終焉、世界的な競争激化…人々は「変化」から逃れられない状況にあった。
この“時代の空気”に合致し、さらに多くの企業研修で配布されることで、書店以上の速度で世界に広がっていきました。
賛否――正論ゆえの物足りなさ
ただし、この本には賛否があります。
確かに「変化を受け入れろ」というメッセージは普遍的ですが、多くの企業がリストラや構造改革の際に社員へ配布したことも事実です。
受け取る側によっては、「結局、私たちが合わせろという話か」と感じられるケースもあったでしょう。
また、読者によっては「動け、と言われても…」というもどかしさが残ります。
変化を察知し、行動に移すまでの具体的なプロセスは、この本の中には描かれていません。
それゆえ、「共感はするが刺さらない」という感想を持つ人も少なくありません。
『迷路の外には何がある?』――信念を疑い、新しい世界へ

続編の背景
『迷路の外には何がある?』は、著者スペンサー・ジョンソンの遺作として2018年に出版されました。
前作で最後まで動けなかった小人ヘムが、今作では主人公です。
舞台は『チーズはどこに消えた?』のその後――チーズを失ったあの日から続いています。
ヘムは依然として、かつてチーズがあった場所に留まり続けています。
周囲には誰もいない。チーズも戻らない。それでも動けない。
この物語は、変化を拒み続けた者がどうやって再び歩き出すのかという、前作では描かれなかった領域に踏み込みます。
物語
ある日、ヘムは迷路の中で、ひとつの赤いリンゴを見つけます。
それはチーズとはまったく違う形と香りを持ち、鮮やかに光っていました。
しかしヘムはすぐに背を向けます。
「リンゴは食べられないものだ」という、過去に植え付けられた思い込みが頭を支配していたからです。
それでも、空腹は待ってくれません。
ヘムは少しずつリンゴに近づき、試しにかじってみる――すると、それは驚くほど甘く、心を満たす味でした。
この一口が、彼の世界を変えます。
「これまでの常識は、本当に正しかったのか?」
リンゴを食べ、知らない道を歩き、ヘムは少しずつ固定観念を手放していきます。
やがて彼は、迷路を抜け出し、広い空と新しい景色の中に立つのです。
核心メッセージ
『迷路の外には何がある?』が伝えるのは、前作とは異なる角度の真理です。
行動を止めるのは、現実ではなく自分の信念
外部の状況よりも、自分の中の「こうあるべき」がブレーキになる。思い込みを疑えば、新しい選択肢が見える
一度“赤いリンゴ”を口にすれば、それまで見えなかった道が広がる。変化は外の世界だけでなく、自分の内面にも起きる
行動の変化は、信念の変化から始まる。
なぜ続編は意味があるのか
前作『チーズはどこに消えた?』は、「変化を察知してすぐ動け」という初動の重要性を説きました。
しかし、多くの人はわかっていても動けないまま、年月を過ごします。
その背景には、過去の経験や周囲から刷り込まれた固定観念が横たわっています。
続編は、この内面の壁を扱っています。
“赤いリンゴ”は、環境や状況そのものではなく、新しい可能性の象徴です。
それを拒むのは外部要因ではなく、自分が抱えた古いルールやラベルなのです。
読後感
私はこの続編を読んで、初めて前作の空白が埋まった感覚がありました。
「変化に対応しろ」と言われても動けなかった理由――それは、方法論ではなく、自分の中の“当たり前”に縛られていたからです。
行動の前に、信念の棚卸しをする。
それができて初めて、人は本当に迷路の外に出られるのだと思いました。
比較と補完関係:地図とコンパス

『チーズはどこに消えた?』と『迷路の外には何がある?』は、同じ世界を舞台にしていながら、その役割はまったく異なります。
片方だけを読むと見える景色は半分だけ。
2冊を通してこそ、「変化の入口」と「出口」が一本の道でつながります。
| 役割 | 『チーズはどこに消えた?』 | 『迷路の外には何がある?』 |
|---|---|---|
| 主題 | 変化の察知と初動 | 思い込みの解除と継続 |
| 主人公 | ホー(動いた人) | ヘム(動けなかった人) |
| メッセージ | まず動け | 視野を変えろ |
| ゴール | 新しいチーズを見つける | 迷路の外の世界を歩く |
1作目は、地図のような存在です。
あなたを取り巻く環境がどう変わっているのかを察知し、進むべき方向を示してくれる。
しかし、地図を持っていても、歩き出せなければ目的地には辿り着けません。
2作目は、その地図とセットで使うコンパスです。
道半ばで立ち止まりそうになったとき、古い信念を修正し、視線を新しい方向へ向ける。
「変化を続ける力」を内側から支える道具が、この続編の本質です。
私が2冊を通して感じたのは、「動くこと」と「動き続けること」は別物だということです。
一歩目の勇気は、一瞬の勢いで出せることもある。
けれど、道中で壁にぶつかったとき、古い信念や固定観念に足を絡め取られ、歩みが止まってしまうことは珍しくありません。
地図だけでは、方向はわかっても進めない
コンパスだけでは、どこに行けばいいのかわからない
この2冊は、まさにその両方を補完し合う関係にあります。
1冊目で環境の変化と初動の重要性を知り、2冊目で自分の内面を見直す。
そうして初めて、“迷路の外”という広い世界にたどり着く準備が整うのです。
変化は“行動”と“信念”の二段構え
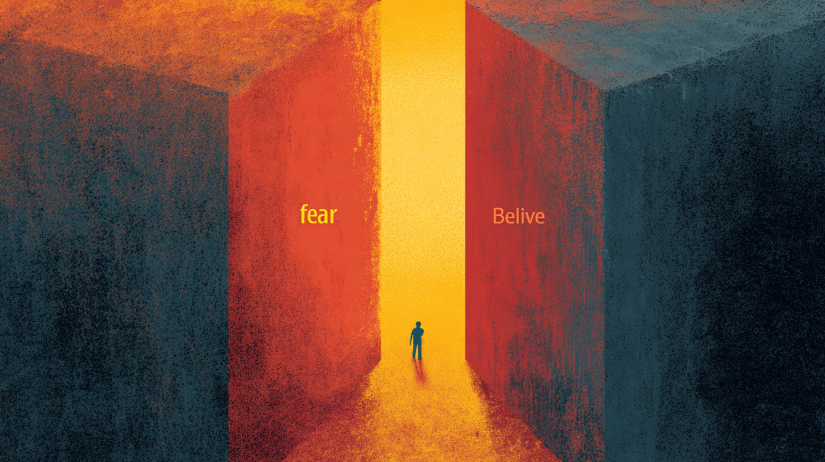
多くの自己啓発書は、「動け」と言います。
それは間違ってはいません。実際、最初の一歩を踏み出せば景色が変わることも多いでしょう。
けれども現実には、動けない理由の多くは外部環境ではなく、自分の内面にあるのです。
行動の壁=恐れや不安 → 『チーズはどこに消えた?』が効く
信念の壁=思い込みや固定観念 → 『迷路の外には何がある?』が効く
例えば、職場で新しいプロジェクトが立ち上がったとき。
あなたはその変化の波に乗りたい気持ちがありながらも、
「失敗したらどうしよう」「今のやり方で十分じゃないか」といった感情に足を引っ張られるかもしれません。
これは行動の壁です。前者の本が、「まずはやってみよう」と背中を押してくれるでしょう。
しかし、いざ動き出しても、思うように結果が出なかったり、これまでの経験則と食い違う状況に直面すると、
「やっぱりこれは自分には向いていない」「こういう方法はダメだ」という、過去の枠組みが顔を出します。
これが信念の壁です。後者の本は、「その考え、本当に正しい?」と静かに問いを投げかけてくれます。
行動と信念、この二つの壁は連動しています。
行動が止まれば信念は固まり、信念が固まれば行動はさらに減る。
この負のループから抜け出すためには、外側(行動)と内側(信念)を同時に揺らす必要があります。
『チーズはどこに消えた?』は、あなたを一歩目に導く外側の火種。
『迷路の外には何がある?』は、その火を消さないように燃やし続ける内側の風。
この2冊を通して読むことは、変化の入口と出口、両方の扉を開くことに等しいのです。
今日からできる一歩

ここまで読んで「なるほど」で終わらせないために、今この瞬間からできるシンプルな行動を3つ挙げます。
全部やらなくても構いません。まずは1つ、5分だけでも動くことが大切です。
1. 自分の“チーズ”を書き出す
いま自分が守りたいもの、欲しいものは何か。
仕事・人間関係・健康など分野ごとに3つずつ書く。
┗「これが私のチーズだ」と言えるものを視覚化します。
2. 変化の“匂い”を点検する
最近、数字・人・環境で小さな変化はあったか?
毎週1回、3分だけでいいので、日常に潜む変化の兆しをメモします。
┗小さな違和感は、大きな変化の前触れです。
3. “赤いリンゴ”を探す
「自分には関係ない」「やる意味がない」と避けてきたことは何か。
それを1回だけ試す(本を1章読む/人に連絡してみる/新しい場所に行く)。
┗結果よりも、「やってみた」という事実が信念をゆるめます。
まとめ:迷路の外は、意外とすぐそばにある
『チーズはどこに消えた?』が教えてくれるのは、変化は避けられないという事実。
『迷路の外には何がある?』が教えてくれるのは、変化を阻むのは自分の信念だという真実。
この2冊は、単体でも価値があります。
けれど、セットで読むことで見えるのは、変化の入口と出口をつなぐ一本の道です。
入口では「動く勇気」を、出口では「信念を手放す軽さ」を。
その両方がそろって初めて、人は迷路の外へと歩み出せます。
迷路を出るのに必要なのは、大きな勇気や劇的な決断ではありません。
ほんの小さな一歩と、固くなった信念を少しだけ緩めることです。
あなたの“次のチーズ”は、案外すぐそばにあるかもしれません。
そして、その向こうに広がる“迷路の外”は、まだ誰も見たことのない景色なのです。
どちらの本もAmazon Audibleで聴くことができます!
Kindle Unlimited・Audible・flyer の比較表
読書をお得に楽しむ方法!
「本を読む時間がない…」「買う前に内容を知りたい…」
そんなあなたには 3つの選択肢 があります!
Kindle Unlimited なら 月額980円で200万冊以上が読み放題!
Audible なら プロのナレーションで耳から学べる!
flyer なら 10分で本の要点をサクッと理解!
Kindle Unlimited・Audible・flyer 比較表
| サービス | 特徴 | 無料体験 | 料金 |
|---|---|---|---|
| Kindle Unlimited | 200万冊以上が読み放題 | 30日間無料 | 月額¥980 |
| Audible | プロの朗読で耳から読書 | 30日間無料 | 月額¥1,500 |
| flyer | 10分で本の要点を学べる | 7日間無料 | 月額¥550〜 |
どれが自分に合う?選び方のポイント!
じっくり読みたいなら →Kindle Unlimite
スキマ時間に聴きたいなら →Audible
要点だけサクッと知りたいなら →flyer




